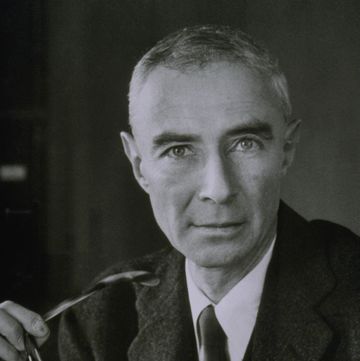ロマノフ朝の最期を描いたNetflixのドキュメンタリー新シリーズ『ラスト・ツァーリ:ロマノフ家の終焉(The Last Czars)』をご存じでしょうか。第1話には、皇帝ニコライ2世の腕にある、大きな龍のタトゥーがあることで世界的に注目されています。
それは短いシーンなのですが、とても印象的です。
ニコライ2世役を演じる俳優が、自分の腕のタトゥーを隠しそびれたのか…と疑った視聴者も少なからずいたようです。しかし実際に、皇帝ニコライ2世の腕にはタトゥーが確かに入っていたのです。
それは1891年(明治24年)、皇帝となる数年前のこと。ニコライが皇太子時代(当時23歳)に日本を訪れています。暗殺が企てられたりもし(大津事件=1891年(明治24年)5月11日、滋賀県大津町で警備にあたっていた警察官の津田三蔵に突然斬りつけられ負傷した暗殺未遂事件)、穏やかなことばかりの日本旅ではありませんでしたが…。
1891年4月27日、ニコライ皇太子ご一行は長崎へ到着します(以降5月19日まで日本に滞在)。どうしても長崎の町を探索したかった彼は、人力車で市内見物に出かけたそうです。そして、(小説『お菊さん(Madame Chrysenthème)』で有名なフランスの作家)ピエール・ロティの真似をして、ニコライ皇太子は右腕にドラゴンの刺青を夜9時から翌朝4時まで、計7時間かけて彫ったのです。
ちなみにこの作家ロティは、『お菊さん』の冒頭で日本人について、「何と醜く、卑しく、また何とグロテスクなことだろう」と書いており、同時代に同じように日本と深い関わりのあったポルトガル外交官ヴェンセスラウ・デ・モラエスや、日本国籍を取得したギリシャ人作家パトリック・ラフカディオ・ハーン (日本名:小泉八雲)のような、日本に対する深い愛情や情熱は欠如していたと評されています。
当時のニコライ皇太子は、長崎の印象について日記の中で「長崎の家屋と街路は素晴らしく気持ちのいい印象を与えてくれる。掃除が行き届いており、小ざっぱりとしていて彼らの家の中に入るのは楽しい。日本人は男も女も親切で愛想がよい」という感想を書いています。
また彼は先のロティへの憧れからか、小説『お菊さん』を読みふけっていたそうで、長崎で一時的に「日本人妻を得たい」という欲求があったそうです。
そして長崎に到着した夜、ニコライ皇太子は長崎市内稲佐(いなさ)に駐留しているロシア海軍の士官8人が、いずれも日本人妻と結婚していることを知り、「私も彼らの例にならいたい」と考えたそうです。が、「こんなことを考えるなんて、なんと恥ずかしいことか。復活祭直前のキリスト受難週間が始まっているというのに」と、自重したことも記されています。
1891年5月3日はロシア正教の復活祭に当たるため、それまでニコライ皇太子は斎戒(飲食や行動を慎んで、心身を清めること)のため公式行事を避けることになっていました。そのため、日本側は5月4日まで公式行事を組まなかったのです。
そして5月4日、ある種の“宗教的障害(復活祭)”から解放されたニコライ皇太子は、長崎市民から熱烈な歓迎を受けます。長崎とロシア太平洋艦隊との30年以上にわたる長い付き合いは、長崎市民がロシア人に対する友好的な態度を育むこととなっていたそうです。彼は日記の中で、「ロシア語が話せる人々の数に驚いた」と記しています。
同日夜ニコライ皇太子は、ギリシャの王子ゲオルギオスと一緒にお忍びで稲佐におもむき、ロシア士官と日本人妻たちに会います。そして、二人の芸者が躍りを披露します。ニコライ皇太子の日記には、「全員が少し酒を飲んだ」とだけ記されていますが、当然彼の護衛役を務めていた日本の私服警官も彼らの後をつけており、その晩の宴に関する日本警察の機密報告書には、ニコライ皇太子の日記には記録されていない詳細が記されています。
「ロシア人一行は丸山(長崎の花街)の芸妓5人を招き酒宴を催し、芸妓が躍り、二人の皇子はロシアの歌をうたった。その夜遅く、二人は諸岡マツという女が経営する西洋料理店を訪れた。二人は朝の4時まで帰らなかった」「マツは二人の皇子のために住居二階に秘密の宴会を手配した」
長崎を去るには忍びなかったであろうニコライ皇太子ご一行は、その後、薩摩(鹿児島)、神戸、京都へ向かい、日本に対して終始友好的な心情を抱いていたことは、彼が記していた日記からうかがえます。彼は日本の建物に入るたびに、「靴を脱ぐべきかどうか?」と常にたずね、日本文化に対しての敬意を示していたとのこと。
しかしその後、歴史的大事件(大津事件)が起こる滋賀・大津に足を踏み入れることとなります。
大津事件に対して多くの日本国民の感情としては、ニコライ皇太子に対して同情を示し、その事件の首謀者である津田三蔵へは憎しみを示していたようです。事件後のニコライ皇太子の日記の中には、「日本国民が街頭に跪(ひざまず)き祈るように合掌して許しを請う姿に感動した」と記せられています。
しかし日本では、津田三蔵と他の日本人全員を区別するよう発言に気をつけていたニコライ皇太子でしたが、実際の彼の心象としては、この大津事件に遭遇して以降、日本人に嫌悪感を抱くようになったとの見解もあります。ウィッテ伯爵によれば、「皇太子は日本人を指して『猿(ヒヒ)』と言っている」と回顧録の中で記しています。
この大津事件が13年後の日露戦争に向かう、静かなる第一歩だったのかもしれません…。
さて、タトゥーの文化が世界的に広まったのは、ここ150年ほどの間だと言われています。もちろん、縄文・弥生期の日本ではすでに、世界でも有数の入れ墨文化を有していたと考えられていますし、2,500年前のアジア中央部にあるアルタイ共和国の王女とされるミイラの腕からも、ほぼ完全なカタチで入れ墨が残されたまま発掘されています。ですがここでは、より一般的な意味での入れ墨文化のことになります。とは言え、皇族たちの間という、特権階級からはじまったのですが、20世紀に差し掛かろうとするその時代のヨーロッパになります。この時代に皇族たちの間で、タトゥーが流行となったのです。
明治期に来日したイギリスの王子たちや、さらにルーズベルト、チャーチル、スターリンまでもが刺青を入れていたのです。
明治期の日本は“文明開化”が咲き誇り、「野蛮」として禁止された日本の刺青ですが、それをいわゆる「文明国」の西洋の王室関係者や貴族が求めたのです(その様子を詳細に考察した元ケンブリッジ大学図書館日本部長を勤めた小山騰氏著『日本の刺青と英国王室 明治期から第一次世界大戦まで』も、ぜひ目に通してみてください)。
他にもイギリスでは、クラレンス・アヴォンデイル公に叙されたアルバート・ヴィクター・クリスチャン・エドワード王子、さらにヨーク公であったジョージ・フレデリック・アーネスト・アルバート王子(後のイギリス王、ジョージ5世。エリザベス女王の祖父)なども、モチーフは異なるものの、タトゥーを入れていたようです(十字架や、ニコライ2世と同じようなドラゴンのタトゥーだったという説があります)。
アルバート・ヴィクター・クリスチャン・エドワード王子、ジョージ・フレデリック・アーネスト・アルバート王子の父親であるエドワード7世もまた、ジルースルム(エルサレム)・クロスのタトゥーを入れていたと言われていますし、さらにはピョートル大帝も、タトゥーを入れていたと言われています。
時代を超えて、やはり日本と海外でも刺青に対する思いは違うようです。
6話からなる『ラスト・ツァーリ:ロマノフ家の終焉』は、Netflixで配信中です。そんな目で、海外大河ドラマを観るのも視野が広がっていいかもしれません。
参考文献:ドナルド・キーン『明治天皇 下巻』角地幸男訳、新潮社
保田孝一『最後のロシア皇帝ニコライ二世の日記 増補』朝日新聞社
Source / Town&Country
Translation / Kazuki Kimura
※この翻訳は抄訳です。