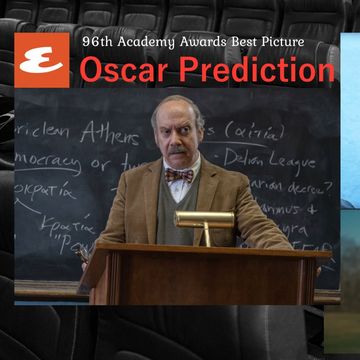「今度の週末は、家族で映画でも観ようかな」と思ってNetflixを開くと、まるでデジャヴ(既視感)のような思いに駆られるかもしれません。なぜなら、Netflixでは2022年12月9日から 『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』が配信を開始しているからです。とは言え本作は、このよく知られた童話に対して独自の解釈を行っていることもすぐに感じることができるでしょう。
まず、タイトルにも入っている監督名デル・トロと言えば、オスカーを獲った『パンズ・ラビリンス』(2006)や『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017)をはじめとして、ダークで不気味な作風が持ち味のファンタジー映画の名手です。そのとおり本作も、ピノッキオの顔に彫り抜かれた軋(きし)んだ笑みから、同じスタイルがはっきりと見て取れるはずです。ですが、この公開についての何かがどうも漠然とではありますが、とても親しみのあるニュアンスを放っているように思えてならないのです。
人形職人のゼペットじいさんと、語り手となるコオロギのジミニー・クリケットが出てくる1940年公開のディズニーオリジナル版長編アニメーション映画『ピノキオ』が頭に浮かんでくるのは当然ですが、つい最近も目にしたような…そう言えば他にも、「ピノッキオ」のリメイクってあったよな…と。
ピノッキオ・マルチバース⁉ 2022年「ピノッキオ」が3作も公開
先に答えを言わせてもらえば、そう、2022年の1年間で他にも「ピノッキオ」のリメイク作品はありました。実際のところこのデル・トロ版の前に、すでに2作の「ピノッキオ」リメイク映画がありました。
もしあなたが、「2022年は、ピノッキオのリメイク作品は一本でも必要だったか?」と思っているような人なら、もう少しだけ私の話を聞いてください。私の鼻には(ピノッキオのように)嘘発見器は内蔵されていないので、これを信じるか信じないかはあなた次第ですが…。2022年に3作目として公開されたピノッキオ、この『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』こそ2022年のベスト・ピノッキオだと思っています。
1年間で3作の「ピノッキオ」映画の公開は、さすがに多すぎて対応しきれないというのは私にも分かります。それに対して、いくつかの疑念さえ湧いて来るでしょう。「なんで?」とか、「やる価値あるの?」といった具合に…。実際、1本あっただけでもう十分です。「可哀想な操り人形のくたびれた木の骨をまたぞろ復活させるなんて、もう止めてくれ」と、映画製作者たちに懇願したくなる気持ちもわかります。
ですがこの年、まずはカナダ発の映画製作および配給会社であるライオンズゲートが、ロシア製作の『ピノッキオ(英題“Pinocchio: A True Story”)』(日本未公開)を英語吹き替えで再公開しました。その時点でもはや、「一体なぜ…?」としか思えませんでした。この映画は予告編が公開されるや、「ピノッキオの声が衝撃的だ」という話がネット上でネタ化してしまい、そのせいで作品に対する真っ当な批評がなされることも望めませんでした。
そして次の「ピノッキオ」は、ディズニーの完全実写化でリブートした『ピノキオ』です。ゼペット役にトム・ハンクスを迎えたにもかかわらず、ロッテン・トマトでの評価は28%(2023年1月20日時点)と低い数字にとどまりました。以上2作で比べれば、当然のことながら後者のほうが前者よりもはるかに映画として楽しめます。そこはやはりディズニーです。かと言ってこの映画を観ても、なぜディズニーが82年も前のフィルムを保管倉庫から引っ張り出して再構築したのか、納得の行く理由は見つからないのです。
そろいもそろって、アルゴリズムの変化に対して同じ仮説を読み解いたのでしょうか? 2022年という年になぜか3つものスタジオが「ピノッキオ」の映画化作品を公開することになったのです。しかし実際のところ、その理由は分かりません。原作であるイタリアの児童文学『ピノッキオの冒険』(カルロ・コッローディ著)の出版が140年近く前であることを考えれば、なおさらです。
とは言え、2011年のアメリカでは映画『抱きたいカンケイ』(1月公開)と『ステイ・フレンズ』(7月公開)といったドッペルゲンガー(自己像幻視)のようにストーリーが似通った2本の映画が公開されましたし、1998年にも同じアリを主役にした『バグズ・ライフ』(3月公開)と『アンツ』(10月公開)がどちらも大ヒットしたなんていうこともありました。
2022年のピノッキオも、こういった事例と同じタイプのパラレル・シンキング(並列思考法=思考を交差させない集中的な思考法)の結果と言えるかもしれません(1990年代後半に、アリを描いたコンピュータ・アニメーションが熱狂的人気を博したことに比べたら、美男美女が「身体だけの気楽な関係」という誓いを貫こうとあれこれ試みる2010年代初頭のラブコメのほうが確かに意外性はそれほどないですが…)。
『星に願いを』かけたかどうかはともかく、2022年のピノッキオ・マルチバースは(あえて乱暴に言わせてもらえば)「高熱で浮かされたときに見がちな、おかしな夢の実現化」みたいなもの。いいえ実際に、これは現実として受け入れなければならないものです。
その中で『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』という作品を適切に鑑賞するためには、少なくともある過去を振り返らなくてはなりません。
怪獣大好き! デル・トロ監督のピノッキオがもつ怪物性
ここで、タイトルにデル・トロ監督の名前が入っていることが重要です。それは、「2022年の先行2作とは別物なのだ」と明確な差別化の役割を果たしているだけではありません。タイトルに入っていなくとも、予告編を一瞥(いちべつ)するだけで監督の唯一無二の作家性が指紋のように見て取れます。デル・トロは共同監督マーク・グスタフソンとタッグを組んでストップモーションアニメの手法を採用し、アニメーターによって手作業でパペット(あやつり人形)を使用して、驚くほど触感的な世界を創り出しているのです。
デル・トロは特殊効果・特殊メイクに携わった経歴を持ち、監督作にもそれを活かした作品が多く見られます。そんなビジュアルは、「欠落を抱えていること」や「社会のあり方が自分と合わないこと」といったこの映画の根底にある大切なテーマと密接に共鳴し、互いのシナジー効果で絶妙なアティチュードを浮かび上がらせているのです。
デル・トロが『ヴァニティ・フェア』誌に語ったところによれば、今回、監督がビジュアル化の先行例である1940年のディズニーの『ピノキオ』とは異なる選択をした(ピノッキオを完全に木製にしたことも含め)のは、オリジナルに対する畏敬の念からなのだそう。「私は、『ピノキオ』はディズニー・アニメーションの最高到達点だと思っています。この映画は、最も美しい手描きの2Dアニメーションでつくられていますので」と語っています。
ピノッキオの嘘を肯定。権力への不服従を「祝福」する
主題的にも、この映画は間違いなくデル・トロのものです。ひとつには、病的でグロテスクなものに異なる仕方で光を当て直すという実に彼らしい傾向が見えます。これは原作のピノッキオからも直ちに見い出せるはずです。
デル・トロのピノッキオの背景は1930年代のイタリア。職人として教会の十字架像の修復を続けていたゼペットは、10歳になる息子カルロと二人で仲睦まじく日々を過ごしていました。そこに、二人が暮らす町とは別の町の爆撃を終えた戦闘機が、その荷を軽くするため偶然にもゼペットが働く教会へ爆弾を落としていくのです。そこでカルロはその爆発に巻き込まれ、幼くして亡くなってしまうのでした。
息子を喪った悲しみにくれ、酒に酔った勢いで「呪われた松で息子を取り戻す」と言い出したゼペットは切り倒した松の木の丸太で男の子の姿を模した人形を乱暴につくり上げます。そして決して出来の良くない人形をあらかたつくり終えると作業を中断し、そのまま寝てしまいます。すると、作業机に放置された男の子の人形の前に、本来は滅多に人前に現れないはずの木の精霊が出現。ゼペットを憐れんだ木の精霊は、彼に再び幸せをもたらすよう人形に借りものの命を吹き込んで「ピノッキオ」と命名するのでした…。
その描き方は実に湿っぽく、その他にも多くの箇所でデル・トロはダークなほうへと脚色しています。例えば原作の「妖精」(※ディズニーのオリジナル版におけるブルー・フェアリー)を、ティルダ・スウィントンが声を担当する「木の精霊」に替えたのもその一例と言っていいでしょう(聖書に出てくる、目のたくさんついた羽根をもった熾天使セラフィムの描写に気味が悪いほど似ている気がします)。またこの映画では、不死身のピノッキオが作中で何度も一時的な死に陥っては黄泉の国を訪れ、そこで冒険を繰り広げるのですが、この死後の世界の描写が他に類を見ないものになっています。
ファンタジーを現実の歴史の中に位置づけることを好むデル・トロは、古典的なおとぎ話を題材にした今作にも、もちろんその手法を忍ばせています。『パンズ・ラビリンス』や『シェイプ・オブ・ウォーター』と同じように、『ピノッキオ』の歴史設定は映画の中で大きな役割を果たしています。というのも本作のピノッキオは、20世紀初頭におけるあのイタリアで子ども時代を過ごすわけですから…。
ファシスト式の敬礼をするキャラクターが最初に出てくるところには、少し違和感を感じるに違いありません。ですが、この政治的背景を擁する時代設定こそが、デル・トロ監督がピノッキオのお話がもともと持っていた教訓を覆そうとするときに役に立ってくれるのです。「嘘をつくことへの警告を発するのではなく、むしろピノッキオの不服従を祝福(celebrate)することをここでは目指しました。そのため、操り人形を従順な者のメタファーとして使用しました」と、BFIロンドン映画祭のプレミアでデル・トロは語っています(この映画の中でピノッキオは、何度も何度も死にます。そのうちの一回は、彼がサーカスでベニート・ムッソリーニに対して面と向かって嘲笑したことによって、すぐさま射殺命令が下されるのです。はい、これは冗談ではありません)。
なぜ父は子どものありのままを愛すべきなのか
デル・トロはまた、イタリア・ファシズムのパターナリズム(父権主義=強者が弱者の意志に関わりなく、弱者の利益のために本人に代わって意志決定をする方法論)に対する権威性を利用する形で、もともとの寓話が持つ育児上の教訓をひっくり返し、それに代わってなぜゼペットはありのままのピノッキオを愛するべきなのか?その理由を見せてくれます――どうやったら愛されるに値する「本物の男の子」になれるかをピノッキオが学ぶのではなく…。ひとつの子ども向けのおとぎ話に対する解釈としては、確かにかなり重い荷が背負わされているようにも思えます。ですが、この賭けは見事な成功をおさめているのです。
本作の成功は、「子ども向けの映画そしてアニメーション映画には、今でも大きな賭けに出る価値があるのだ」ということを思い出させてくれるものでした。本作以外にも、『Marcel the Shell with Shoes On(原題)』(2021)などもそうですが、2022年のアカデミー長編アニメ映画賞の最有力候補となった作品は、これと同様の論調を輝かせるための後押しをしています。それは内容を二の次にして、金儲けを最優先するマーケットの真っただ中にありながらもこれらの作品は、年齢の枠を超えてあらゆる人々の心に迫る芸術作品として提供されているからなのです。
子どもたちの理解力を信頼した脚本
細部に至るまで非常に熱心につくり込まれたアニメーションの製作過程に始まって、自らのメイン観客層となるPG=子どたち(※)が持つ理解力を最大限に信頼した脚本、さらには「ピノッキオ」を昔から好きだった人たちに対しても物語から新たな意義を引き出して気づきを与えていました…。
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』は、枠組みが半ば定式化してしまっていたおとぎ話というジャンルに、真の意味で息を吹き返させたのです。もはや、2022年の「ピノッキオ」先行2作のことは忘れていいでしょう。VHSで観た1940年版ディズニーのぼんやりした記憶も、何なら忘れてくれてかまいません。『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』は、どれほど頑なになってしまった心にも、石化した心にだって、入り込むことができるに違いありません。そう、ギレルモ・デル・トロの本作は他の「ピノッキオ」リメイクを、遥か星の彼方まで凌駕しているのです。
※ “Parental Guidance” アメリカでの本作のレーティングで「保護者の判断が必要」というもの。ここでは「保護者の監督下にある子どもたち」の意味で使用されています。ちなみに日本では本作の年齢制限は、映画館ではG「年齢制限なし」で、Netflixの日本サイトでは7+とあり、「7歳以上推奨」と書かれています。
Translation: Miyuki Hosoya