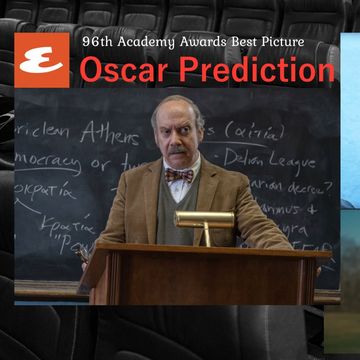映画『オッペンハイマー』。アカデミー賞最多ノミネーションなるか
アカデミー賞で何部門にノミネートされるのか、現地時間2024年1月23日の発表(授賞式は同年3月10日)が待たれる『オッペンハイマー』。クリストファー・ノーランの「最高傑作」との呼び声も高い。先日発表された2024年のゴールデングローブ賞では、8部門8候補となり最多9候補を出した『バービー』を部門数で上回りました。また、クリティクス・チョイス・アワード(放送映画批評家協会賞)では、13部門の候補にあがっています。
「原爆開発苦労話」でも「天才科学者の不運」でもなく
この作品は、最初から一定の危うさをはらんでいました。“西側世界”からオッペンハイマーを主人公に原爆開発を描くとあれば、落とされた側ならずとも心穏やかではいられないのは当然のこと。例の“バーベンハイマー”の騒動により、内容への厳しい批判的視線が送られました。幸か不幸かそのおかげで、「原爆が戦争を終わらせた」というこれまで散々垂れ流されてきた正当化への批判も、この作品にまつわる言説には多かったように思えます。
実際のところ内容も、「原爆開発苦労話」といった単純なものではありません。各界の主役級をずらりと並べた、あらゆる苦難を乗り越え世紀の発明にたどり着く成功譚であっても、日曜夜の地上波で繰り広げられる感動ドラマとは全く異なり、発明したその先に地獄が待っている物語。友情・涙・努力の成果により大量虐殺が起こり、その後の人生が台無しになる話です。
空気が読めない物理学者
そもそもノーランが描くJ・ロバート・オッペンハイマーは、空気が読めません。少し前に流行った言葉で言えば“トーンデフ(tone-deaf)”といった風の人物像を、キリアン・マーフィーは準備期間わずか半年ほどで見事に組み立てています。
学問でも、恋愛でも、結婚生活でも、仕事でも、彼はとことん空気が読めません。おかしなタイミングで挙手、「花はいらない」と拒否する恋人に毎回花束を持参、育児ノイローゼの妻から逃走し、友人夫婦のドアを叩き(しかも深夜に)子守を委託、結婚生活に満足しているのに請われれば元恋人の逢瀬にえんやこら、「やめておけ」と同僚が進言しても、学生たちに持ち上げられて共産主義活動のため研究室を貸与…。
頭はいいのに深く考えないオッペンハイマーは、タバコを切らすことなくいつも何か熱に浮かされているような表情で、悪魔の発明に手をつけている感覚もないまま、“原子爆弾の父”の道をひた走ります。気づくと、容易には止まれないほど多くの人たちを乗せ、暴走トラックと化したマンハッタン計画。そのハンドルはオッペンハイマーではなく、物理学ド素人のトルーマン大統領が握ってしまいました。
悪魔の発明を手に興奮する政治家、軍人、銀行家たちによって自らの発明が翻弄されてもなお意見することなく従順に突っ立っていたオッペンハイマーは、長崎と広島に投下されて初めて自らのトーンデフネスを自戒することになります。
「目の前に山があったから登った」と同じノリで、ものすごく爆発する爆弾をつくりたかっただけ…大量虐殺をするつもりなど毛頭なかったのに…。
責任は取れないが無罪でもない
「発明した自分に責任は取れないとしても、無罪ではない」。そうつぶやくかのように、戦後鳴りやまぬ賞賛と褒賞(ほうしょう)の嵐の中、オッペンハイマーはようやく、自分のトーンデフがもたらした核兵器の脅威へと突き進む世界を眼前に葛藤しはじめます。そうして戦後、新たな“悪魔の発明”水爆に反対の立場をとるように…。
子どものように純粋な熱意の物語は『下町ロケット』とはかけ離れ、むしろ『指輪物語』になり、オッペンハイマーが生み出した「サウロンの力の指…」は世界を混沌に陥れました。その後、なんとか指輪の力を封じ込めようとした彼は、今度は指輪の虜になった人々から「共産主義者だ」と言いがかりをつけられ、原子力委員会を追放されてしまうのです。
原作者カイ・バード&マーティン・シャーウィンと共にノーランが描き出した、頭はいいけれど物事をよく考えないオッペンハイマーが、エミリー・ブラント…もとい、妻キットに胸倉をつかまれ、性格の悪いロバート・ダウニー・Jr.…もとい、政敵ルイス・ストロースに感策を弄されるシーンには爽快感すら感じます。禁断の発明に手を出した罰として。
映画監督も無罪でいられるのか
これは翻って、この作品を生み出したクリストファー・ノーランにも当てはまります。
映画のインパクトを受けるのは監督ではなく、観客であり、社会。世界に投下した作品が結果、どのような影響を人々に与えるのか? つくった側にそれは選択できない。その証拠に、“バーベンハイマー”のミームに興奮した人々が被爆者側の長い苦しみの歴史を踏みにじったわけで、うっかり「いいね!」を押した『バービー』公式SNS担当者の行為が、米ワーナーまで巻き込んで大炎上することになるとは想像すらしなかったはずです。
しかし、実際に事(こと)は起こってしまいました。誤解であれなんであれ。
遺伝子、人工化学、AI、そして映画作品…。科学の責任は科学者には負えないし、映画監督も作品の責任を負えない。「ならば」と、責任を最初から放棄するのか、それでもなお最大限の誠実さをもってときに発明自体を諦めるのか。被爆者の姿を明確に描かなかったことは、ノーランの誠実さか傲慢さか(あえて、加害者側が被害者を勝手に想像して描かないこともまた、誠実さと言えますが)…といった議論も永遠に続けられるであろう映画『オッペンハイマー』は、この世に何かを生み出す全ての人間にそれを問いかけていると捉える――そこに、この作品の価値があるように思えます。
『オッペンハイマー』(2024年公日本開決定 ※詳細未定)
公開決定にあたり、配給会社からのコメントが出されました。全文は以下の通りです。
「弊社ビターズ・エンドは、クリストファー・ノーラン監督作『オッペンハイマー』を 2024 年、日本公開いたします。本作が扱う題材が、私たち日本人にとって非常に重要かつ特別な意味を持つものであるため、さまざまな議論と検討の末、日本公開を決定いたしました。作品を観たうえで、クリストファー・ノーラン監督の手による、伝統的な作劇手法を超越した唯一無二の映画体験には、大スクリーンでの鑑賞が相応しいと考えております。日本公開の際には、観客の皆さまご自身の目で本作を御覧いただけますと幸いです」