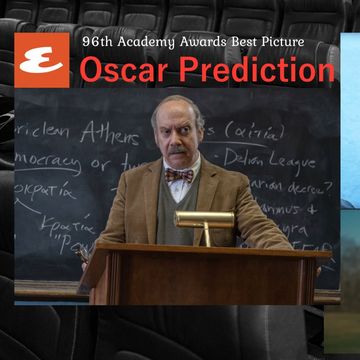『バービー』のグレタ・ガーウィグが、アカデミー賞監督賞候補から漏れました。さらに、主演のマーゴット・ロビーも主演女優賞から外されました。
2024年1月10時点で、世界興収14億4500万ドル*¹(約2120億円)を稼ぎ出したポップ系フェミニスト映画として知られる本作品、そのキーパーソンに対するずいぶんな仕打ちと言えるこの事態はスティーヴン・キングにすら、「どういうことだ⁉(意訳)」と呟かせる衝撃をもたらしました。
『バービー』でケンを演じて助演男優賞候補になってしまったライアン・ゴズリングも思わず、その失望感を長文で発表するに至ったわけです。彼は『ピープル』誌に、「バービーがいなければケンはいないし、グレタ・ガーウィグとマーゴット・ロビーなくして『バービー』の存在しえなかった…世界で最も賞賛された作品に最も貢献した二人が無視されたのは、ありえないことと言えるだろう」といった声明*²を出しています。 しかしながら『バービー』は公開当初から、当のフェミニストたちから一定の批判があったことを考えれば、この結果は当然かもしれません。
ホワイトフェミニズムの誹りを免れない
「barbie+feminist+criticism」などのワードで検索すると、大抵の場合は「議論を巻き起こす…」だの「論争の引き金になった…」だのはたまた「男性差別的だ…」だの、どじょっこだのふなっこだのと、あさっての方向で“批評”する内容でつづられた記事ばかりがグーグル先生に提案されます。そのため、大抵のジェンダー系のご批判は頓珍漢であるという意見はごもっともですし、ただの人形に着想を得たコメディ映画に完璧さを押し付けなくても…と、擁護したくなる気持ちも理解できます。
デジタルメディア「Refinery29」の、「マーベルやトランスフォーマーに同じことを強いてきたか」と疑問視する記事*³にも大いに賛成です。ファミリームービーとしての魅力も十分に兼ね備えた作品で、ジェンダーを軸に脚本を仕上げ、興行的成功まで達成するのはどれほど大変だったことでしょう。複数の候補者が断念した末に任せられたグレタ・ガーウィグの重圧も、計り知れないものがあります。
それでもやはり、作品から漂うホワイトフェミニズムの香りは否定できません。特にインターセクショナリティを考える重要性と、実は女性同士を対立させてきたホワイトフェミニズムの解体が叫ばれる今、メディアがその名のもとに大量消費してきた「フェミニズム=パワーウーマン(マジョリティ女性=エリート・勝ち組)」の構図が搾取と人権の蹂躙に利用されてきたことが暴露されて久しい現時点では、それを笑って見過ごせません。
作品の姿勢そのものが、白人女性に象徴される「男女の間でしかジェンダーを考えずに済む立場」の「勝ち組視点」であることを、対男性との覇権争いに終始するバービーたちが証明しているように残念ながら見えてしまいます。多重のマイノリティ性ゆえに、男性と闘うだけではジェンダーの罠から解放されずにあくせくしている人たちを「勝ち組志向のフェミニズム」が鼓舞…ではなく足蹴にしてきたことを、この作品は意識的に無視したか、無視せざるを得なかったのでしょう。
(この辺りの問題はウーマンリブ時代にすでに議論されており、当時の米フェミニストたちの葛藤をドラマ化した2020年製作のミニシリーズ「ミセス・アメリカ~時代に挑んだ女たち~」*⁴で複数の女性監督たちがそれを見事に描いています)
ジェンダーのパワーバランス(※)は男女の二元論では語れない
皮肉にも、1月14日(現地時間)に開催されたクリティクス・チョイス・アワードの主演女優賞発表時にもホワイトフェミニズムを象徴する現象は起こりました。ホストのチェルシー・ハンドラーが「女性のエンパワーメント」を叫んだ授賞式で、最優秀主演女優賞を獲得したエマ・ストーンが候補となった他の女優たちを賞賛すべくひとりひとりの名前を挙げた際、「グレタ」と呼んだ瞬間にカメラが映し出したのはグレタ・ガーウィグでした。
画面に抜かれたガーウィグ監督が“It's not me. It's not me...”と繰り返し否定してようやく、カメラ(orスイッチャー)は『パスト ライブス/再会』でノミネートされたアジア系俳優グレタ・リー(ちなみに彼女は、ノースウェスタン大学で演劇を学んだ舞台出身のエリート)を映したのです。
「肌が黒でも茶でも、先住民やアジア系、トランスジェンダーでも、障がいをもっていても体型がどうあれ、いかなるジェンダーでも、私たち全員に豊かな人生と、正しく語られる価値があります」
「SeeHer」賞(ジェンダー平等を拡大するような業績を残した女性を称える)を受賞した『バービー』のアメリカ・フェレーラがこんな感動的なスピーチをした今回のクリティクス・チョイス・アワードでも、アジア系の女優が「正しく」映されることはありませんでした。
これは単なる「ミス」と表現するのは難しい。あの流れでエマ・ストーンが他作品の監督の名前を挙げるわけがないのですから。この「ミス」はマイノリティ側が日々味わう、「白人(に見える人)のようには認識されない」侮辱的行為であり、これは歴史がつくり出した構造的な問題の結果と言えます。
もちろん、「(現在、グレタ・ガーウィグの夫でもある映画監督)ノア・バームバックと学ぶフェミニズム基礎講座」とも言える『バービー』は、初心者男性にもアレルギー反応が起きないように“ジェンダー・イシュー”*⁵を解説しているうえ、世代に関係なくみんなで楽しめるエンターテインメントに仕上げた、そして興行的にも、歴史的な大成功を収めた素晴らしい作品であることに間違いはありません。
とは言え、やはり観る側を揺れ動かす一手に欠けていたことは否めません。上品で大人しく、さほど世間を脅かさないフェミニズムは、恵まれた強者の特権です(第一、この脚本の半分はあの、「君なんか死んでしまえばいい!」*⁶と妻に言い放つ男を憐れんだNetflix作品『マリッジ・ストーリー』の監督、バームバックが手掛けているのです。あの物語もまた、男女が闘った挙句に程よく和解するものでした)。
これを『哀れなるものたち』は見逃しません。階級や貧富によって女性たちの間で軋轢が生まれてしまうこと。格差システムや男性の欲望によって女性が女性を搾取せざるを得ない状況になることも描いているのです。
※以下『哀れなるものたち』のあらすじに触れる記載があります。
リプロダクティブ・ヘルス&ライツを無視した『バービー』、グロテスクにアプローチした『哀れなるものたち』
子どもも観られる『バービー』と18禁の『哀れなるものたち』を、こういった視点で比較することがアンフェアであることは重々承知のうえで、アカデミー賞というハリウッドの檜舞台に上げたとき――指摘すべきなのは何より、『バービー』に身体性が欠落していたことです。
あるのは「老い」くらい――出産に関しては軽く触れてスルー。人形なので仕方がないとは言え、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス&ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の視点なくして男女平等は文字通り“ファンタジー”になってしまいます。その点に気味の悪い形でアプローチしたのが、『哀れなるものたち』でした。
「男女それぞれ事情はあるけど、それでもがんばって共存していこうよ」と、散々バービーワールド&現実社会を股にかけてファンシーな男女の覇権争いをした挙句、男と女の和解を促した『バービー』に対し、『哀れなるものたち』は、「男、逝ってよし」と突き放します。
子どもをこの世に生み出す女性の身体と、出産を強制する家父長制のグロテスクな欲望に、後者は物語の終盤近くで「ノーモア・ファルス(男根)中心主義!」と警告を出すのです。上映前の「ノーモア映画泥棒」表示と対を成している…わけがありません。(男根モチーフがそっと美術セットに紛れ込んでいます。隠れミ●キーのように探しながら見るとより楽しめます)
暴論? 新時代に適応できるシン・男性が生き残ればよい
そもそも女性だけで人類の再生産が成立してしまえば、男性は必要ありません。卵子だけ、精子だけでの生命誕生がマウス実験で成功しています。
「オスのiPS細胞(人工多能性幹細胞)から卵子をつくって別の雄マウスの精子と受精させ、子どものマウスを誕生させることに成功した」*⁷ということが、大阪大学と九州大学などの研究チームによって報告されています。逆に中国の研究者らが「卵子の遺伝子を改変せずに働き方を変え、メスだけでマウスを誕生させることに成功した」*⁸と発表したと報道されました。数年前には卵子でも精子でもない幹細胞から「合成」胚を作ることに成功したとオランダの科学者チームが発表*⁹しています。
これら実験の肝は、受精卵と同じ機能を持つ存在を人工的に成功させても結局誕生させるのはメスのマウスだったという点です。
研究チームの代表として大阪大学教授の林 克彦博士(生殖遺伝学)は、「人の細胞から卵子をつくるには今後10年程度かかるだろう。男性同士で子どもを持つことも理論的には可能になるが、今回の研究成果を人で応用していいかどうかには社会的な議論が必要」と言います。生命科学の倫理的問題はもちろんのこと、結局女性に産んでもらわないと生まれない生命なのだとしたら、“受精卵”を前にしたジェンダー不平等というさらなる問題も生まれます。女性と同じように人類の再生産に男性が関わるためには、1994年の映画『ジュニア』のアーノルド・シュワルツェネッガー同様、”妊娠”して”出産”しなければなりません。では男性の身体で生まれた個体がタツノオトシゴのように妊娠できるようにする研究は“受精卵”と同じくらいなされているのでしょうか。
もちろんこれに対し、「マッドサイエンティストの所業」と言い放つ者も存在するでしょう。『哀れなるものたち』の原作もまた、フランケンシュタイン博士を引き合いに出していることから、人工的生命創造を決して賞賛しているわけではないことがわかります。生命の営みにおいて男女両方とも欠かせない状態が確保されているほうがある意味平和かもしれません。しかし現時点ですら、妊孕性、もっといえば「女性に産ませる能力」に依拠する男性陣のアイデンティティ・クライシスが年々ますますシリアスになっていることは、各国で起こっている性と生殖に関する保守現象を見れば火を見るよりも明らか。ファルス中心主義の暴力的支配から少しずつ利益を享受してきた男性たちが、自分たちの存在の危機をどうにかして回避したいと考える気持ちは理解できます。
でも、それをケアしてあげる優しさは必要なのでしょうか。
その「危機感」の根本にあるのは、強者男性がその他大勢を支配する一神教的もしくは家父長制的階級支配システムの副産物である…ということにそもそも無自覚な思考能力。これは害悪でしかないのでは? もっと言えば、「過去の“男性性”の復権に1ミリたりとも得などない」と言えるではないでしょうか。
得があるのは、“労働者の抑圧(社会の歯車であれと強制する)に「男らしさ」を利用できる資本家たちのみ”、としたのは誰だったでしょうか…。であるなら、そういった方々にはさっさとお亡くなりになっていただき、真のジェンダー平等時代に適応できる男性のみに生き残ってもらいましょう…そう考えることもできます。
サラリと以上のような内容を映画にしてしまうヨルゴス・ランティモスとその仲間たちのほうが、多種多様なバービーたちとケンたち同士の差をフラットに、性と生における男女の非対称性をまるでないかのように見せてしまった『バービー』より、よっぽどジェンダーにおいてラディカルな印象を残します。
グレタ・ガーウィグとその仲間たちは、男性に気を遣ったのか、マテルに気を遣ったのか、はたまた別の何かに気を遣ったのか(少なくともCBSのインタビュー*10ではものすごく全方向に気を遣って発言)…は不明ではあるものの、良くも悪くも和解案を提示しました。
その控えめさは、少なくとも2024年においてもなお、多数派が異様なほどに「父なる神」を崇拝する宗教国家アメリカ合衆国、特にまだまだジェンダーの平等からかけ離れているハリウッドにおいては、危険な妥協策と受け取られても仕方がありません。
男がいなくとも続く世界で「君たちはどう生きるか」
なぜなら、アメリカではいまだに「プロライフVS.プロチョイス」の選択が政治的議題になってしまうほど、「女性の価値=母体としての価値」のスキームはしつこく残っており、自分の生命と子宮内の胎児は秤(はかり)にかけられ、時には自らの命を捨てることも強いられていると言えるからです。
ロー VS. ウェイド判決から半世紀を経て、宗教グループの影響下、憲法上で中絶の権利が奪われてしまった宗教国家において、ハリウッドが語る「男と女の和解」など高みからのご意見でしかないでしょう。現在のアメリカは、女性が命をかけて生と生殖に関わる健康と権利を獲得する闘いの真っただ中にあります。
男性はそもそも生命に責任をもてないし、生命の役にも立てない――。存在の耐えられない軽さを突きつけられ、レゾンデートル(存在意義)を主張するべく、「俺の子ども産めや」とばかりに性加害とそれに準じる行動をとる哀れな男性たちに、フランケンシュタイン博士と彼の「創造物」クリーチャーを併せたような男性医師バクスターの姿を通し、「君がいなくても子はできる」とランティモスは諭しているかのようです。
「ならば、君たちはどう生きるか」
ランティモスが男性陣に突きつける問いは、煤けた色彩と真っ黒な(ときに笑えない)笑いに満ちています。ヴィヴィッドカラーで観る人の気持ちを明るくさせた『バービー』と対を成すように。
『哀れなる者たち』(上映中)
【あらすじ】
自ら命を絶った不幸な若き女性ベラ(エマ・ストーン)が、天才外科医ゴッドウィン・バクスター(ウィレム・デフォー)の手によって、奇跡的に蘇生することから始まる。大人の身体のまま新生児としていちから世界を学んでいくベラは、恥の概念や偏見を学ばないまま貪欲に世界を吸収し、急速に知を獲得していく。やがて不平等と不自由を学び、世間の抑圧から全力で逃げ延びた末に、ある結論に達する。
監督:ヨルゴス・ランティモス(代表作:『女王陛下のお気に入り』)
出演:エマ・ストーン、マーク・ラファロ、ウィレム・デフォー、ラミー・ユセフ ほか原作:『哀れなるものたち』(早川書房刊)
[脚注]
*1:statista 2024より
*2:『ピープル』誌掲載の声明
*3:「Refinery29」の記事
*4:Disney+、Apple TV+で配信中
*5:ジェンダー・バイアス等によって、あるジェンダーに属する者の政治的、経済的、法的、社会的な評価や扱いが差別的かつ不平等である状態が是正されるべき課題であると捉えて、問題提起されていること
*6:映画『マリッジ・ストーリー』のセリフより
*7:科学雑誌『nature』の掲載記事より(参照:yomiuri.co.jp)
*8:参照:yomiuri.co.jp
*9:『nature』
*10:CBSインタビュー「60minutes」での発言
※ ここではジェンダーの権力格差・覇権に性的マイノリティだけでなく人種や経済力など多くの要素が関わってくることを説明したため、性別二元論(gender binary)との混同を避けるため小見出しに「パワーバランス」を加筆いたしました[2024.02.17]