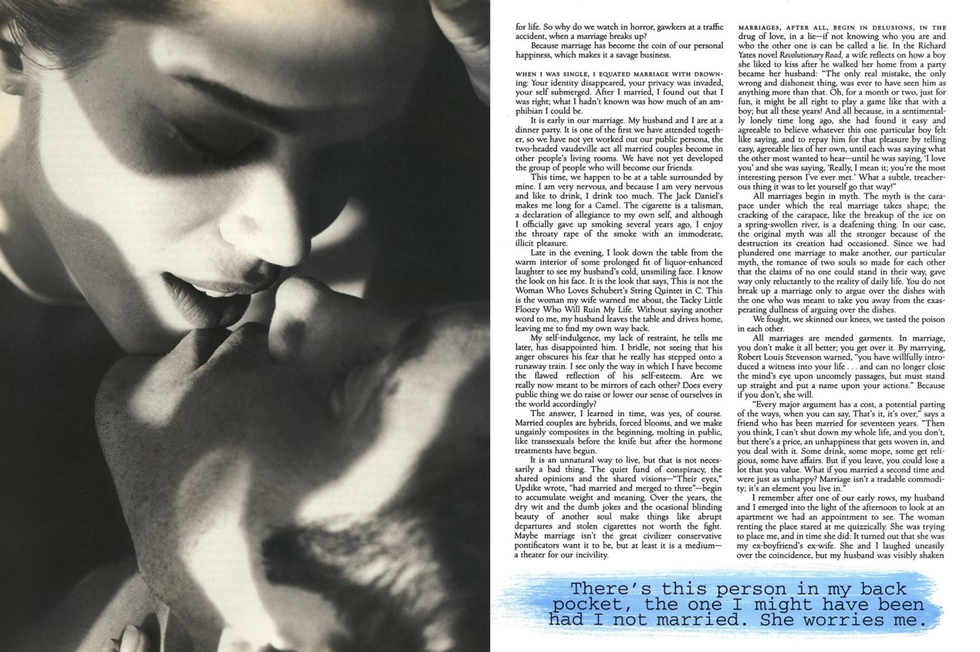1990年代多くのメディアに恋愛に関するエッセイを残したリン・ダーリング。ハーバード卒の才女であり、才能あふれるライターであり、担当だった名物編集者と結婚した90年代の“理想的”な道を歩んだ末に彼女が見た「結婚」の本質とは?
連載第1回はこちら
出版業界が儲けるためにブランド化された「結婚」
出版業界は、「結婚」がいい撒き餌(まきえ)になると嗅ぎ当てています。過去10年間で、結婚をテーマにした本は900冊を超えています。『結婚の終わり』『良い結婚』『対等な関係における愛――仲間としての結婚の実際』『男と結婚』『タフ・マリッジ 困難な関係をうまくいかせる方法』『結婚1年目に起きること』『親密なテロリズム エロティック・ライフの劣化』『ずっと一緒!――生き生きしたロマンチックな結婚のための愛の方法125』などなど…。
これらの本は、冷静な判断と論理的な解釈を用意してくれています。戦略や交渉を教えてくれます。私たちをカオスから守ろうとしているのです。「キラキラした、IKEA的な結婚生活はどうですか」と語りかけてきます。「木材の色は明るく、ラインはすっきりして、どんなインテリアにも合うデザイン――少し自分で組み立てなくちゃならないけれどね!」というわけです。しかし、現実の結婚とは、目も当てられないほど醜いビクトリア朝時代の壮大な建築物なのです。詰め込みすぎで、むやみやたらと奇抜で、汚れを覆うのは黄ばんだカバー、かぎ爪型の脚には、傾かないようにマッチブックをひとつ、ふたつ挟まなくっちゃ!というような…。
結婚には義務感と責任感、野蛮さと礼儀正しさが奇妙に混ざり合っています。やがてそれは、長い時間を一緒に歩んだ2人の人間だけが生み出すことのできる、気遣いと残忍さとが複雑に入り組んだ「習慣」という形の道徳を織り上げるのです。
結婚生活でドラマクイーンに
結婚して初めてのバレンタインデーに、夫がバスタオルをくれました。赤いタオルで、いわゆる「二級品」と呼ばれる、糸のほつれや傷などがあるためバーゲンの棚に置かれるようなものでした。買い物袋に蝶結びのリボンがついていて、ギフトラッピングになっていました。
それを開けたとき、泣いたのを覚えています。私はすごく怒っていました。そのタオルは、太陽を覆い隠す(暗雲の)メタファーでした。ちょうど2人での日常が次第に形になってきて、暮らしの中の物音に安心感を覚えるようになったところだったのに、それをつんざくような悲鳴があがったかのようでした。
タオルはその悲鳴のメタファーでもありました。あれは、私たちのロマンス史上、最も日の高かった真昼の出来事。夫に悲しいほどの欠落があると判明した、感情的で歴史的な出来事でした。今だから言えるのですが、あの頃の私たちはまだ本当の意味では、結婚していなかったのです。私たちはまだティーンエイジャーの恋愛モードで、つまり「彼は私を愛しているの? それとも愛していないの?」状態にありました。劇的な出来事に夢中になり、求愛や情熱の感情を相手に投げつけていました。そこでは視線ひとつで、突如として感情的な危機が爆発するのでした。
なぜ、あんなに自分が怒ったのか? 今ではもう思い出せません。理由はきっとこんな感じだったのではないでしょうか。私はこの男にすべてを賭けた、かつ彼は私の考えていたようではない、彼はフォード・マドックス・フォードを読んで泣く男じゃない、この選択、この男で私の値打ちが決まる、そして彼はこういうタイプの男、そう、タオルをくれるタイプの男なのだ、と——。
この話を思い出すと、今では微笑ましく思えます。
結婚がまだ鏡のようなもので、その鏡に映し出されるのは慎重に築き上げられ、簡単に打ち砕かれる自惚れだけだった頃の話です。今では夫は、毎年バレンタインデーにバスタオルをくれます。バレンタインデーのたびに私は笑います。あの出来事は私たちの神話の一部になっているのです。しかし、この笑いそれ自体はエッジの効いた注釈になっています。いかにいろいろなことが変わったか、いかに私たちがお互い変わったのか、いかにこのジョークで笑い合う2人の人間が、互いの期待と失望に、もう消えることのないほどの色に染め上げられているか、いかに私たちの人格が結婚相手をレンズとして、それを通って屈折した人格と合わさってできているか、こうしたことについての注釈です。笑いはベッドスプレッドみたいなもので、お互いに相手の中に残したしこりや、お互いに施した色々な手術の傷跡、夫婦を成り立たせるために抑制された情熱などを覆いかくしてくれます。
テレビが漂白した結婚の本質的異常性
私が夫と出会ったとき、彼は結婚していました。夫とその妻は15年間連れ添い、子どもは3人いました。私がこの話をしたのは、自分で抱いていた自分という人間のイメージと、他人の人生に大混乱をもたらしかねない人間のイメージが、今でもなかなか結びつかないからです。
私はこれまで、自分が事故に遭ったとしても、めちゃくちゃになるのは自分だけだというある種の安心感を抱き続けていました。だからこそ今、苦い正義感を覚えてしまいます。なぜなら、時間をかけて話し合い、調整を重ね、彼の子どもたちは私にとってすごく大事な存在となり、彼の前妻と私とはお互いの人生にとってなくてはならない存在になれたにもかかわらず、悲劇的な破局が訪れたこと。しかも、私の眼の前でそれが展開されているからです。そして、このカルマ(業=行為の結果として蓄積される「宿命 )の衝突にも似た結果を引き起こしたのは私自身なのです。
私は彼と結婚しました。そして考えたのです、「次は何?」と。ですが私は、その「次」なる話の展開はわかりませんでした。私たちに用意された筋書きはわずかです。「彼女が昇進するまでは、私たちは幸せだった」「彼が他の女性に出会うまでは、私たちは幸せだった」「子どもたちが依存症治療施設に入るまでは、私たちは幸せだった」など。ハッピーエンドで終わる物語は、さらに数が少なくなります。
私は独身の頃、何年もの間オフィスのボードに、恍惚の瞬間を収められたある夫婦の写真を貼り続けていました。その写真の夫婦は、結婚50周年の記念パーティーでお互いの周りを回るようにして踊っていて、年老いた妻の顔には夢中になって喜ぶ少女の表情が浮かび、夫の顔には髑髏(どくろ)が歯をむき出しにして笑っているように見える写真です。彼らは化石化した愛の概念に閉じ込められているようで、私には怖く感じられました。そんなわけで私は、それを自分への警告として貼り続けていたのです。
こんなことにならないように…と。
昔、ある夏の日、私はある老夫婦を見かけました。2人は手をつないで砂浜をずっと散歩していました。ピンク色のたるんだ身体にTシャツと短パン。それは子どもが着るような服で、肉がおかしな状態で垂れ下がっているため悲惨な感じになっていました。ですが彼らは実に幸せそうでした。私が彼らを見て思い浮かんだのは、「願いは叶えられました。でも、そこには条件がつけられていました」という台詞です。
テレビは、世間一般の結婚観を二度と戻らないほど歪めました。ホームコメディは、結婚というものの持つ本質的に異常性をともなった契約である面を拭い去ってしまったのです。そう、メンデルが行ったような奇妙な遺伝子の実験…寝室やその他、ほの暗い闘技場でひそやかに成長し、途方もない形にねじ曲がっていくことを。
それに代わって私たちに手本として与えられたのが、ウォード&ジューン・クリーバー夫妻(※1)という柔らかなパラダイムです(ルーシー&リッキー・リカード夫妻<※2>のほうが、より真実に近い描かれ方と言っていいかもしれません。リカルド夫妻の間には、厳しい最後通告、欺き、激しい喧嘩、妨害された野心などがありました。とは言え、それはドタバタコメディの喜劇的な演出のためではありましたが…)。
- ※1 1957年放映開始、ホームコメディ「ビーバーちゃん」に登場する夫婦。50年代アメリカの典型的な夫婦としてよく参照される。
- ※2 1951年放映開始、シチュエーションコメディ『アイ・ラブ・ルーシー』に登場する夫婦。シリーズは現在でも人気があり、国民的に知られたドラマ。ルーシー&リッキーを演じた実の夫婦ルシル・ボールとデジ・アナーズの結婚の裏側は『愛すべき夫妻の秘密』(2021年)として映画化され、夫妻はニコール・キッドマンとハビエル・バルデムによって演じられた。この結婚も離婚に至った。
テレビの中で、かつて結婚は神のごとく永遠のものでした。新たな世紀になろうとしている現在(※)、テレビでは最後の子どもが巣立つのと同時に夫婦のどちらかが死んでいます。けれどもホームコメディでは、現代になって寿命が伸びたことで、数多ある不幸な結婚に対しての伝統的な治療法が奪われてしまった…という不都合な事実を決して認めませんでした。
- ※ 本稿初掲載は1995年
死すべき定めによって促されなくとも、ジョン・アップダイクは、結婚の中に誕生と死とを見て取っていました。彼は「結婚が終わりになってしまうということは、確かに理想的とは言えないが…」と、『メイプル夫妻の物語』(1979年)の序文で書いています。「しかし、この世のものにはすべて終りがあるし、それに、永続性がなければすべて無意味に帰すると考えたら、正直言って何もこの世に残らないことになってしまう」と続けています(※)。
- ※ 引用は、岩本巌訳『メイプル夫妻の物語』(新潮文庫、1990)より
野蛮なビジネス
~結婚は幸福を買うための「貨幣」~
私たちは90年代の厳しい現実に、耐えられそうにありません。何もかもコントロール下に置きたがるこの国では、子どもを持とうとする人が専門家を雇って、妊娠するのにいちばん有利なのは何月なのか? という計画を立てるのです。
ワシントン大学の研究によれば今や結婚さえもある方程式のもと、意のままに操ることができるそうです。「結婚生活を良好な形で維持するためには、プラスの相互作用とマイナスの相互作用の比率が実際にどのような値であることが必要か、数値化することができる」と研究者たちは主張しています。彼らの研究から分かったのは、「満足している夫婦とは、理想との比較において自分たちの結婚がどうであれ、プラスの時とマイナスの時の比率が5対1を保っている夫婦である」ということです。はい皆さん、電卓を出してみてくださいね!
私たちはまるで都会人に農園を、遊び人に礼拝の説教をやらせようとするかのごとく、自分たちを説得して何かをやらせようとしているかのようです。ノスタルジアこそが私たちにとっての最高の芸術形式である今、結婚もまた失われた夢のひとつになってしまいました。その夢が、かつて一度も取ったことのない形で再生されようとしています。
ひねくれた頑固者の哲学者だった故クリストファー・ラッシュ(※)は、現代の私たちの態度に冷ややかな目を向けています。彼の考えでは、台頭している経営者や専門家といったエリートたちは実験的な価値観の持ち主であり、伝統を軽んじ、その場限りで深い関わりを持とうとはしません。また彼らは、結婚をはじめとする諸制度を存立させている道徳的規範を粉々に打ち砕きます。「この新しいエリート、実力主義者たちは忠誠心や自分の言動に対する責任感、お互いの一番の存在であることへの誇りといった結婚における基本的な資質を欠いている」とラッシュは書いています。
- ※ クリストファー・ラッシュ(1932-1994年)。アメリカの歴史学者、社会批評家。『ナルシシズムの時代』(1978)が全米図書賞を受賞。
分かりましたか? これは有罪ですね。私たちはあまりにも賢く、あまりにも豊かで、そしてあまりにも愚かでもあるため、生涯にわたって互いに結婚し続けることはできないのです。では、なぜ私たちはある結婚が破綻するのを、交通事故現場の見物人のように恐怖におののきながら見つめるのでしょう。
それは結婚が、私たちの個人的な幸福を買うための貨幣となっていて、そのことで結婚が野蛮なビジネスになっているからです。
「溺死」する結婚
独身時代、私は“結婚を溺死と同じだ”と思っていました。自分のアイデンティティが失われ、プライバシーが侵害され、自分が水没してしまう…と。結婚後に私は、その自分の考え方が正しかったことを知りました。私が知らなかったのは、自分がどれほど「両生類」になり得るかということでした。
結婚して間もない頃のことです。夫と私はディナーパーティーに出席していました。それは私たちが一緒に出席する最初のパーティーのひとつで、私たちはまだ公的なペルソナを完成させていませんでした。つまり、他人の家のリビングルームで、すべての結婚したカップルがなるところの双頭のボードビリアン(※)の芸はまだ完成させていなかったのです。のちに私たちの友人となる人たちのグループも、まだできていませんでした。
- ※ ボードビルとは、歌や劇、曲芸などを取り混ぜたショー。フランス発祥で19世紀にアメリカへ伝来し、形を変えながら20世紀にアメリカで流行。ボードビリアンはボードビル演者のこと。
このとき私たちは偶然にも、私の友人に囲まれたテーブルに着くことになりました。私はとても緊張していて、緊張するとお酒を飲みたくなるので、結果として飲み過ぎてしまいました。ジャック・ダニエルのせいで、キャメル(※)が恋しくなります。タバコは私にとってお守りであり、自分自身への忠実を宣言するものであり、オフィシャルには数年前に禁煙したのだけれど、無節操で不埒(ふらち)な快感を味わいながら煙が喉を破壊するのを楽しみました。
- ※ 煙草の銘柄名
夜も更けて私は、酒に酔ったがゆえの長い発作的な笑いの中でぬくぬくとしていました。ふとテーブルを見下ろすと、夫が笑いの消えた冷たい顔をしているのが目に飛び込んできました。私は彼の顔に浮かぶこの表情を知っていました。
「この女は、シューベルトの弦楽五重奏曲ハ長調を愛する女ではない」「この女は、自分の妻が注意するよう警告を与えてきた女だ」「この女は、私の人生を破滅させるちっぽけでみすぼらしい自堕落な女だ」という表情です。夫は私に何も言わずに席を立ち、車で家路につきました。残された私は、自分で帰る手段を見つけなければなりませんでした。
私の自堕落さ、そして自制心のなさに失望したと夫は後に教えてくれました。そのとき私のほうは、ツンとして顔をそらしました。彼のその怒りが、「自らが暴走列車に乗り込んでしまった」という恐れを単に覆い隠しているだけとは気づかないまま、私は不快感を露わにしたのです。自分は、「彼の自尊心の鏡像としては欠陥のある存在になってしまった」というふうにしか思えなかったのです。私たちは今、本当にお互いの鏡になっているのでしょうか? 人前で何か言ったりやったりするごとに、それに応じて世間での「私たちらしさ」についての感覚が増えたり減ったりしていくのでしょうか…。
時とともに私が学んだその問いへの答えは、もちろんイエスでした。夫婦は交配種であり、無理やりつくり出された花のようなもの。私たちは最初のうち、不格好な合成物になりますが、ときに人前で脱皮したりするのです。性別適合手術以前だけれど、ホルモン治療は既に始めているトランスセクシュアルのようものです(※)。
- [編集部注]※この文章は、マジョリティ側に起きている現象を例えるため、マイノリティ側の当事者にとってはセンシティブな内容を不躾(ぶしつけ)に利用して喩えたものになります。ですが、当時だけでなくごく最近まで続いてきたマジョリティ側の差別意識・特権の表れであり、これが大手出版社で通用していたのが90年代センスなのだという事実を隠蔽しないためにも、ここではそのまま記載しています。
結婚は不自然な生き方だと思います。ですが、必ずしも悪いものではありません。一緒にする企みごとのための秘密資金、共有された意見、共有されたビジョン…こうしたものの重要性や意義が増し始めています。
ピューリッツァー賞も受賞している作家ジョン・アップダイク(1932–2009年)は、「彼らの目は結婚して3つになった」と記しています。年月を重ねる中で、乾いたウィットや間抜けなジョーク、さらに相手のふと垣間見せる目も眩むような予想外の美しさによって、突然の旅立ちやタバコが盗られたといったようなことは争うまでもないものになるのです。
結婚は保守派の論者たちが「そうあってほしい」と望むような、文明化のための素晴らしい制度ではないのかもしれません。ですが少なくとも、結婚はメディア、媒体ではあります。良識ある「市民」の枠からはみ出す、私たちの野蛮さを表現するための劇場なのです。
第3回へつづく
Translation: Miyuki Hosoya