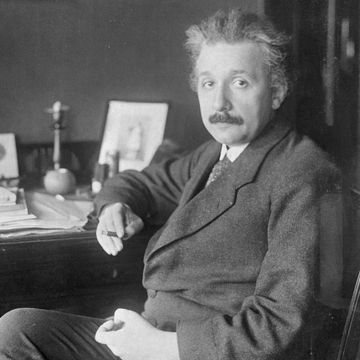昨年頃から急激にAI画像生成がはやり始めて、趣味目的や金もうけ目的の人がごっちゃになって群がり、あちこちでAIフォトコンテストなどが開かれている。そういえば筆者も、AI画像生成を試みる記事『「AIアバター」作成におじさんが挑戦!出来栄えに満足した後に気づいた真の楽しみ』を執筆したが、あれは楽しかった。
AI画像を生成する人は、「呪文」と呼ばれるプロンプトを用いて、AIに指示を出す。「プロンプト」というといかにも専門的でハードルが高く感じられるが、日本語入力に対応しているサービスなら、たとえば「武藤・美男子・中年」と入れるだけでそれらしき画像が仕上がってくる。
「AI絵師」や「呪文者」などと自称・他称する、AIを使って画像を生成する「アーティスト」たちは、この呪文に詳しくて、注文をより具体的にするために何十個という呪文を入力して画像を生成するのである。
アマチュアが趣味の範囲でAI画像生成に精を出しているのを見るのはいかにも「カルチャー」という感じがするが、この新技術は「金になるぞ」ということで人が殺到していて、その辺がちょっとドロッとしている。
たとえばAmazonのKindleストアには「AI写真集」がいくつも並んでいる。これはつまりAIアーティストが生成したAI画像をまとめた画像集である。誰かが生成した画像を見るために一冊いくらの写真集は、買うには正直ハードルが高いが、サブスクの『Kindle Unlimited』内に陳列されていれば「ちょっとのぞいてみるか」くらいの気持ちで読まれやすく、読まれたページ数が多いほど報酬も上がる。お手軽な副業の出来上がりであり、ここを極めて本業となす人もいる。なお、AI写真集の内容はガイドラインのギリギリを攻めた際どいものも多いらしい。
『週刊プレイボーイ』のグラビアを飾ったAIモデル・“さつきあい”の生成は『週刊プレイボーイ』編集部が行ったとのことで、どのような動機に基づいてそれが行われたかはわからないが、ビジネスとして見れば目指されているところは同じである。グラビア撮影にかかる諸費用を一切すっ飛ばして、呪文を唱えるだけでグラビアが完成するのであるから、おいしいビジネスには違いない。
AIモデルのかわいさや技術の進歩に驚嘆する声も多く、「AIグラビア」という言葉はTwitterトレンドにもなった。ここまでがAIグラビア騒動の陽の面であるが、陰の面が結構深刻である。
まず、もっと表層に見える問題は、例のAIモデル“さつきあい”が実在の誰それに似ているのではないか、という指摘である。
「似ている」とちまたで名指しされている女優の名前を挙げることは当記事では避けるが(そうした形でこの騒動に加担したくないため)、本人の了解を得ない形で、その女性が、“さつきあい”となってグラビアで再利用されるなんてことであれば、あまりにもひどいではないか――というわけである。
では実際、“さつきあい”とその女性が似ているかだが、こればっかりは主観によるので断言はできない。「そっくり」という人もいるし「まったく似ていない」という人もいる。だから問題は、「似ているか似ていないか」というあいまいな部分ではなく、現実に起きている「特定の人物に似ているという臆測が立ち、かつそれが問題視されること」という部分にある。
誰かに似ているとなれば肖像権が問題となる。「特定の誰かをモデルにした」として生成されたAIモデルなら肖像権の侵害に当たるであろうが、「たまたまそっくりに見える」AIモデルが肖像権を争う上でどう判断されるかは未確定で、今後の課題として残されているらしい。
肖像権と関連して著作権も大きい課題である。
AIモデル・AIイラストの生成は、AIが学習した大量の画像データをもとに行われる。大量のデータを元に新たな一作品を生み出す過程は人間の創作活動と似ている。しかし、人間ならばどうしたってそこに一さじ加えられるであろう“その人らしさ”、すなわちオリジナリティーが、AIには想定しがたいので、AIはどれだけいってもパクリではないか――という意見がまずひとつある。
そしてパクリの元、すなわち種々のデータをAIが勝手に学習することが、そもそも著作権に引っかかるのではないか――という見方も出てきている。
実際に米国では、「自分の作品を勝手にAIの学習データとして用いられた」という著作権侵害の訴訟が複数起きている。「○○風」という呪文を唱えれば、AIは容易に指定通りの○○風の作品を仕上げることができ、これが著作権をひどく侵害する可能性がある、ということである。
一方、日本はというと、著作権法の2018年の改正で追加された著作権法・第三十条の四で、「AIは、だいたいどんなデータでも無許諾で学習してオッケー」とされた。比較的近年改正された条文で、技術の進歩とAIの発展を願った懐の深いかじ取りに思われたが、まさかその改正数年後に、AIがこれほどすごいことをやってのけるとは思っておらず、学習データの著作権について再検討の必要に迫られている。
<参考>
著作権法
文化庁 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について
総じて、AI生成の進歩が速すぎて、法律も利用者の意識も追いついていない。
社会や人がもう少し技術を受け入れた頃合いで、“さつきあい”のごときAIモデルが登場していたら、さほど大きな問題にはならなかっただろう。AIアーティストたちは、著作権・肖像権、および「似ている」といわれるかもしれない実在のモデルに配慮する意識が育っているだろうし、そこが至らなかったとしても法律がカバーするはずだろうし、一般の受け取り手はいちいち「これ大丈夫…?」と不安になることなく安心してコンテンツを楽しめるはずだからである。
しかし、そうした状況に到達する前にAIモデル・AIイラストがここまで普及してしまった。
必要な問題意識や議論をするために、“さつきあい”が登場した…とも捉えることができる。
ただし、「今の苦労も将来のために必要だった」的な美談としてだけで済ませるとまずいのは、本件に関して被害者がいるかもしれない点である。似ていると名を挙げられていた実在のモデルが“さつきあい”自体に対して、また今回の騒動に関して何を感じただろうか。
AI生成者(『週刊プレイボーイ』編集部)から本人にコンタクトを取っていいかもしれないが(本人が意に介していなかった場合、やぶへびとなって本人を不快にさせるおそれがあり、悩ましい)、もし本人発信でなんらかのネガティブな意思が表明されるのであれば、編集部は必ず、しかと対応すべきだろう。法の整備が整っていない今だからこそ、個々人が意識と関心を持つべき、難しい局面である。
新技術を利用してカルチャーを一歩推し進めようとした『週刊プレイボーイ』編集部の姿勢に敬意を評しつつ、筆者もAI生成で遊ぶ一個人として、一層の注意を払っていきたい。