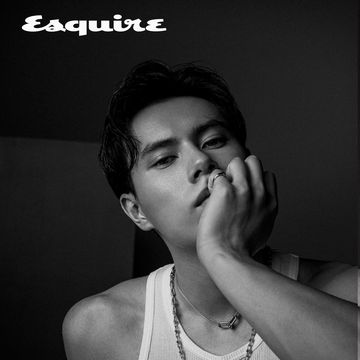11月最後の日曜の朝、私(ミッチェル・S・ジャクソン)は目が覚めてからすぐに、真新しいスニーカー「Off-White x Air Jordan 2 Low OG」にはっ水スプレーを吹きかけていました。履き古したようなデザインではあるものの、本当に汚くなってしまってはかなりショックなので…。2回目のコーティングをしていたのです。このスニーカーの小売価格は250ドルでしたが、誰もが欲しがっているこの靴を小売店で手に入れるのはいつ実現するかもわからないので、転売業者から3倍以上の値段(750ドル以上)で買うことになりました。3倍以上の値段がついているのは、MJ(マイケル・ジョーダン)ブランドだからでもありますが、それ以上に「Off-White(オフ-ホワイト)」とのコラボレーションであることが大きな理由です。
つまりは、ヴァージル・アブローのブランドだからなのです。
市販のままでも高価な価格のスニーカーであるのに、私はその価格の3倍以上の値段を支払ったということで、いささか悔恨(かいこん)の念も抱いてもいました。そこで私はその後、クローゼットの中をウロウロとしました。愚かな私は、心の中でスニーカーの分を穴埋めするだけの転売できるアイテムを探すつもりで、クローゼットの洋服をあれこれあさり始めたのです。
そろそろ終わりにしようとしていたところ、やはりヴァージルの素晴らしい作品、5年以上前に購入した「Off-White」のグリーンのジャケット(400ドル以上だったと思います)が目に留まりました。
「このアイテムなら、リセールがうまくいけば元を取れるどころか、少しおまけが出るかもしれないな」と、心の中でつぶやく私。そのコートをラックから外して手に取り、確認すればするほどその重さに感嘆するばかりです。クロームのジッパーの新品同様の輝きに気づき、ペイントされた文字を手でなぞりながら「売るべきか? 売らざるべきか?」とブツブツと呟きながら悩んでいました。
ヴァージル・アブローが
積み上げてきた歴史
正直に言うと私は、彼の(このブランドの)初期からのファンではありません。実際2018年に、最初の「Off-White」のMJコラボレーションが発売されたときには、怪訝(けげん)さしか抱いていませんでした。ジョーダン(や他のブランド)商品にヴァージルの名前が付いた、基本的にはレプリカのようなものの価値が、「どうしてこんなにも高くなるのか?」と理解できなかったのです。
でも、考えてみてください。そのようなアイテムの価値とは、常に「ストーリー」上にあるものです。例えばこのコラボレーションスニーカーは、ミラノでつくられた正規品。そしてこのブランドは、長年Ye(カニエ・ウェスト)との関わりがあり、さらにそのカニエと親しいこのクールなファッションデザイナーがデザインしたものなのです。
そうしてヴァージルというデザイナーのストーリーは、彼の生前からファッション界の伝説として君臨してきたのです。
1980年9月30日、イリノイ州ロックフォードでガーナ移民の子としてヴァージルは誕生します。その後、大学で社会基盤、大学院で建築を学びます。大学院在学中、レム・コールハース設計の建築中の建物(マコーミック・トリビューン・キャンパス・センター)の影響で、ファッションに興味を持つようになった彼は建築を学びながらTシャツをデザインするようにもなります。そして、シカゴのプリントショップでデザインを手掛けているときに、ミュージシャンのYeと初めて出会うのでした。
そしてその1年後、2010年にYeはヴァージルを彼のクリエイティブエージェンシーであるDONDAのクリエイティブディレクターに任命。そうして2013年に、自らのブランド「Off-White」を立ち上げます。
彼が積み上げてきたキャリアの中でも特に歴史的な事件を言うなら、おそらく、2018年に「ルイ・ヴィトン」のメンズ アーティスティック・ディレクターというファッション界で最も切望される仕事に、黒人として初めて就いたことでしょう。
そうして私は過去10年ほどの間に、ヴァージルについて知れば知るほど、誰とのコラボレーションかにかかわらずヴァージル・アブローのブランドへの興味は高まっていき、いつの間にかバーニーズやサックスの陳列棚で彼の服を手に取っては、試着室の鏡の前でそのフィット感や加工、デザインに対しての憧れを強めていったのです。
それでも私のような労働者は、その破格の値段に躊躇してしまい、決して買うことはありませんでした。その後なんと、気に入っていたディスカウントストアに「Off-White」のアイテムが登場し、私はその後の数年間で(ディスカウント価格でもまだ高い)タウン用スウェットやTシャツ、パーカーを購入し、さらにアーミーグリーンの「Off-White」のジャケットを購入しました。そのジャケットはデザインやつくりがいいだけではなく、自分の良さを最高に引き上げられるような気にさせてくれたのです。
ではここで改めて、「なぜ、そのジャケットを買ったのか?」そしてその後、「ニューヨークで最初に住んだアパートの家賃と同じくらいの価格で販売されていたスニーカーを、なぜ買うことになったのか?」について、簡単に考えてみたいと思います。
10代の頃、
リサイクルショップで
服を買っていた
ずいぶんと昔のこと、1980年代終わりから90年代前半にかけて、母と弟と私の小さな家族は、叔父の一人が副店長として働いていた聖ヴァンサン・ド・ポール教会のリサイクルショップへよく行っていました。当時叔父は母のために、こっそりよい商品を取り置きしておいてくれたり、他人が不要になった服がかかったラックから、3人の誰かの分、または全員分を見つけるまで集めてくれていました。
最悪の日には、「手ぶらで帰るよりマシだ」とビニール袋に入れたボロボロの古い服を手に、物足りない気持ちで店をあとにしていました。逆に最高の日には、「ほぼ新品の服を袋いっぱいに詰め、まるでお金持ちにでもなったかのような幸せな気分」とともに店をあとにした日もありました。
そんな聖ヴァンサン・ド・ポール教会のリサイクルショップへ通うことで、予算内で掘り出し物を手に入れをする方法(叔父はときどき、母に最高額の割引をしてくれた)を学びましたが、この体験は子ども時代の一種のトラウマにもなりました。
「この店で買い物をしているところを近所の人に見られても平気だった」という記憶は、ほぼありません。誰かに私が貧乏である証拠を握られることが怖くて、「その人たちも困っていたかもしれない」などと思いつきもしませんでした。「誰かが自分のお下がりの服を私が着ているところを見つけ、多くの人の前でそれを口外するのではないか?」という恐怖に常に怯えていたのです。運良くその不安から逃れられたとしても、古着の匂いに悩まされてもいました。それはかなり鼻につき、肌に染み込んでくるような不快な匂いだったのです。
このリサイクルショップに通っていた時代のおかげで、私の中には、「何としてでも自分の貧しさを覆い隠し、別の叔父がクローゼットの中で腰の高さまで積んで集めていた高級雑誌のページに掲載されていたような服をいつか着るぞ!」という強い欲求が生まれたのです。私たちが買っていたあの頃の古着は、「ヴィンテージ」と呼ばれるようなものでは当然ありませんでした。
古着を買う=恥ずかしい
という考えを
払しょくしてくれたアブロー
2013年にヴァージルが「Off-White」を設立したとき、私は38歳。つまり、ヴァージルがしばしば言っていた、「Everything I do is for 17-year-old version of myself.(私がすることはすべて、17歳のときの自分のためだ)」「I'm always trying to prove to my 17-year-old self that I can do creative things I thought weren't possible.(私はいつも17歳の自分に、不可能だと思っていた創造的なことができることを証明しようとしています)」という彼自身が抱くターゲットからは、私は20歳ほど年上だったわけです。設立当時よりも、今だからこそ理解できたことがあります。それは、「ヴァージル自身のストーリーが、どれだけ彼のブランドに付加価値を与えてきたか」ということです。
私が「Off-White」の商品を買うことは、古着屋の棚で必死に商品を探している姿を見られたり、学校に来ていった服から古臭い中古品の匂いがすることを友だちに気づかれる…ということに対する、不安を打ち消す手段でもあったのです。
つまり私にとって、「Off-White」の商品を身につけることは、ラッパーのスリック・リックのトレードマークである、ゴールドチェーンや巨石のような大きさのダイヤモンドスタッド、「ジェイコブ」のカラフルな腕時計のような派手さはありませんが、「貧しさを感じさせるようなものは二度と身につけたくない」と考えていた自分の心意気を表すものだったのです。
そんなことを思いめぐらせていた日曜日の朝、私は結局、そのジャケットを元のラックに掛け、そしてクローゼットの扉をしっかりと閉じました。もうリセールなどしません、絶対に。たとえ誰かに懇願されたとしても…。
Source / ESQUIRE US
Translation / Keiko Tanaka
※この翻訳は抄訳です。