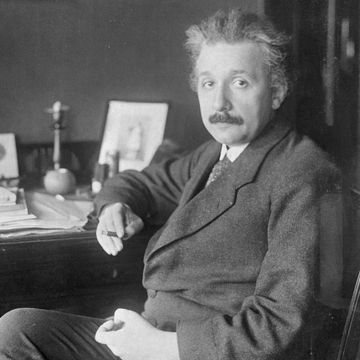イタリアでの経験を基にした小説『アダノの鐘』で1945年にピューリッツァー賞小説部門を受賞しているジャーナリストであり、戦争の英雄として称賛されているジョン・ハーシー(John Richard Hersey)が、原爆投下直後の広島での取材に到るまでの真相が明かされました。新しい本「Fallout」の抜粋は、ジョンハーシーが現在伝説の広島旅行をどのように計画したかを明らかにしています。
1945年の晩秋のこと。従軍記者ジョン・ハーシー(John Richard Hersey)と『ザ・ニューヨーカー』誌の副編集長ウィリアム・ショーンは、2人でランチを食べていました。「ショーンの考えるパワーランチというのは、アルゴンキン・ホテル(The Algonquin Hotel)のローズルームでとるオレンジジュースとシリアルのことさ」ということなので、特別な出来事だったわけではなさそうです。このホテルは長い間、ニューヨーカー』の優秀な悪徳寄稿者たち、雑誌記者、編集者、評論家などのたまり場としても使われてきました。毎日のようにホテルのレストランにランチの時間に集まり、ウイットに富んだ会話を楽しむ"Vicious Circle"と名づけた社交サークルをつくっていまたそうです。"Vicious"というのは、日本語では「不道徳な」や「意地の悪い」、「悪名高い」などといった意味になります。そんなサークル名をつけるところは、皆さんジョーク好きでウイットに富んでいた証しではないでしょうか。
最初は、パーゴラルーム(後のオークルーム)の長方形のテーブルで食事をとっていましたが、人数が増えたため、当時のマネジャーであったフランク・ケースにより、ランチの場所はローズルームの円卓(ラウンドテーブル)に移され、資材にそのサークルの名も"アルゴンキン・ラウンドテーブル"と呼ばれるようになったそうです。
話を戻しましょう。ハーシーはショーンと彼の上司で、『ニューヨーカー』の共同創業者兼編集者であるハロルド・ロスのために、すでに米軍に関する記事をいくつか書いたことがありました。当時アメリカ海軍中尉だったジョン・F・ケネディが艇長を務めた魚雷艇がソロモン諸島で日本の駆逐艦に衝突され、乗組員が死亡した際の記事は有名です。
弱冠31歳にして、ピュリッツァー賞受賞作家となり、戦争の英雄として称賛され、国際的に尊敬される記者となったハーシー。終戦後、再び海外特派員として取材を始める時が来たと判断したハーシーは、数カ月におよぶ大掛かりなアジアでの滞在を計画していました。
ランチを食べながらハーシーとショーンは、記事のアイデアとして広島について話し合いました。長崎原爆投下を目撃した記者がいる唯一の報道機関だった「ニューヨーク・タイムズ」紙は、広告主に対して「原爆と原子時代の幕開けを世界にスクープした」と自慢しており、ある『ニューヨーカー』の記者は「世界史上最大のニュース記事だ」と評していました。
しかしハーシーとショーンは、1945年8月6日と9日に日本に投下された原爆をめぐる一連の報道には、本質的な何かが欠けていると感じていました。それまでの報道に欠けていた不穏な点に気づいたのです。
「それまでは、原爆の威力と街に与えた被害の大きさについての報道がほとんどでした」と、後にハーシーは振り返っています。
広範囲にわたって報道されているように見えましたが、実際には景観や建物に対する被害に関するものが多かったわけです。広島の原爆投下からしばらく経過していましたが、原爆が被害者に対して与えた影響については、ほとんど報道されていませんでした。
ひと足先に現場に到着した連合国側の記者たちは、広島のたどった運命に関する悲痛な情報を伝えようとしていましたし、東京には野心的なベテラン特派員が何十人もいました。しかしながら放射性降下物について、そして「ニューヨーク・タイムズ」紙が表現した「標的エリアを覆っていた砂塵(さじん)と煙の分厚い雲」の下の広島がどうなっているかについて、大々的で包括的な記事を書いた記者はいませんでした。
しかも報道の数は、次第に減る一方だったのです。
広島や長崎についての見出しは、他の記事に取って代わられるようになってしまったのです。アメリカ国民が毎朝新聞を開くと、目に入るのは米軍の帰還やヨーロッパの復興、ドイツのニュルンベルク裁判、そしてもちろん米ソ対立の激化などのニュースでした。
ハーシーとショーンが、東京にいる記者たちに課せられた制限を知っていたかどうかはわかりませんが、感づいてはいたはずです。当時のアメリカのジャーナリズムは狭い世界でしたし、ハーシーの知り合いの特派員の多くは、占領下での状況を取材するために日本に派遣されていました。いずれにしても占領が始まった最初の数日間の混乱の中、広島に関する最初の報道が出て、米政府が守りの姿勢に入ったのは明らかでした。ワシントンD.C.でもマッカーサーのいる東京でも、米政府関係者は直ちに原爆の影響に関する報道を封じ込めようと奔走し始めていたのです。
1945年9月、ロンドンの「デイリー・エクスプレス」紙に「Atomic Plague(原子疫病)」という驚くべき見出しの記事が掲載され、広島の被ばく者を襲う謎の恐ろしい病気について報道されました。(「シカゴ・デイリーニュース」紙のジョージ・ウェラー記者も、長崎の被ばく者を悩ませている恐ろしい「病気X」について報道しようとしていました。ですが発表前に発覚し、“封印”されてしまいました)
「デイリー・エクスプレス」紙のバーチェット記者の記事に、世界中が恐怖した直後、アメリカの大手報道機関の編集者たち(ロスとショーンも含まれていたと思われます)は同年9月14日、米陸軍省から極秘の手紙を受け取ります。
それはトルーマン大統領に代わって、原爆に関する情報を出版物に掲載することを制限するよう求めるものでした。陸軍省はすぐに、「これは戦時中の検閲の延長線上にあるものではない」とコメントしました。新聞や雑誌の編集者には、「核問題に関する記事を事前に陸軍省に提出し、審査を受けるように要請しているだけである」と述べ、原爆に関する機密情報が外国の手にわたらないようにするための、「最高レベルの国家安全保障のためだ」と説明しました。
その頃マスコミを正し、アメリカ人の道徳心を落ち着かせるための政府の記者会見が急きょ行われるようになりました。占領が正式に始まる前から、トルーマン大統領の報道官のチャールズ・ロスは陸軍省にメモを送り、1945年7月16日に原爆実験「トリニティ」が行われたニューメキシコでメディアイベントを行うことを提案していました。それは長期的な放射能の被害がないことを示し、原爆の影響がないことを国民に示し、安心してもらおうと考えていたわけです。
「日本からのプロパガンダ(宣伝戦)が続いていることを考えると、いいアイデアだと思う」と、メモには書かれています。
同年9月9日に、マンハッタン計画のリーダーであるレズリー・グローヴス少将とロスアラモス国立研究所の所長ロバート・オッペンハイマーが自ら、ニューメキシコ州の原爆実験場を約30人の記者に案内しました。記者たちは表面に放射線はほとんど残っていないと聞いていましたが、「地表に残っている放射性物質が、靴底に付着しないように念のため」と、特別な白い保護カバーを靴にかぶせていたそうです。
「日本人は、『放射線による死者が続出している』と主張していますが、それが本当だとしても、死者はほんの少数です」と、グローヴス少将は記者に話しました。
参加した記者たちは、政府の言葉に従いました。「ニューヨーク・タイムズ」紙の特派員の1人であるウィリアム・ローレンスは、「日本軍は今もなお、われわれが不当に戦勝に勝利したと印象づけるためのプロパガンダを続けており、同情をあおって協定内容を緩和させようとしている」と報道しました。
ちなみに彼は、たまたま陸軍省の給与担当者を務めており、「タイムズ」紙の人事記録によると1944年4月から「タイムズ紙から原爆プロジェクトに出向していた」のだそうです。彼は放射能による死という「広島物語」はまったくのフィクションであると、ニューメキシコの地に立つことで「無言の証言を行った」と書いています。また、ガイガーカウンターによると、「地表の放射線量は微々たるレベルにまで減少していた」とも付け加えています。
米国政府とマンハッタン計画のメンバーは、実験兵器の影響がどのようなものになるか、事前に知っていたわけではありません。そして今になって、広島と長崎の「死の実験室」(連合軍側の特派員の表現)に関する調査に奔走していました。被ばくした街に放射能が残留しているのか? 市民にどのような影響を与えているのか? 早急に調べる必要がありました。これはアメリカが日本の被曝者の治療をしようと考えていたからではなく、「すぐにでもこの街を、米軍が占領しなくては…」と考えていたからなのです。
同年9月にニューメキシコでこのイベントが行われる直前、グローヴス少将はマンハッタン計画の副官であるトーマス・ファーレル准将を、広島の影響を調査するために急きょ日本に派遣していました。
そして同9月8日、広島に到着したファーレル准将とマンハッタン計画の科学者たちは、後に記者が呼ぶところの「スポットチェック」を実施します(参加したアメリカの物理学者の1人は広島の被害状況を見て、「一般人の目には1000機のB-29による攻撃のように見えるだろうが、アメリカは単に効率の良い装置を使ったのだ」と感じたそうです)。ワシントンからのファーレル准将へのプレッシャーは強く、「グローヴス少将はファーレル准将に怒りの電報を送り続け、最新情報を要求していた」とチームの1人が回想しています。
チームは大急ぎで結論をまとめ、放射能のほとんどが大気中に吸収されたため、「街中の放射能は最小限にとどまっている」と報告しました。チームによる簡単な調査結果に基づいてグローヴス少将は記者たちに、「被曝で亡くなった日本人はほんの少数で、広島には基本的に放射能は残っていない」と伝えたのです。
そしてグローヴス少将は、「永遠に住んでいられますよ」とコメントしています。
東京に戻ったファーレル准将は帝国ホテルで記者会見を開き、広島での調査結果を発表しました。同年8月6日に投下された原爆によるガンマ線被曝で、少数の日本人が死亡したことは認めました。ですが、「広島に関するこれまでの報道は誇張されたものだ」ともコメントしています。
会見は順調に進んでいましたが、「デイリー・エクスプレス」紙のウィルフレッド・バーチェットが、「自分はたった今、広島の原子疫病の取材から帰ってきたところだ」と発言します。
彼は汚れ、疲れ果てて、体調を崩していました。彼が満員の記者の前で広島で見てきたことについて問いただすと、ファーレル准将は「入院している人たちは、爆風と火炎の被害者であり、大きな爆発が起きたあとでは普通のことです」と答えました。それでもバーチェットは被ばく者たちの間で起こっている奇病について、さらに食い下がりました。
ですが、「君は日本のプロパガンダの犠牲になってしまったようだね」と、バーチェットは一蹴されてしまいます。
この記者会見に続く数カ月間、グローヴス少将は独自のPRキャンペーンを続け、彼の核兵器を慈悲深い兵器として国民に認識させるよう全面的に努めました。1945年11月、日本への原爆投下とその後遺症について証言するために議会に召喚されたグローヴス少将は、最終的に原爆都市での死者の一部は放射線が原因であることを認めました。ですが、「医師たちは、放射線障害は安らかに死ぬことができると断言していた」と、上院原子力特別委員会に報告したのです。
秋にマンハッタン計画の実験場や請負業者を訪問した際に、グローヴス少将は演説を行い、原爆投下に対して罪の意識を抱く必要はないと聴衆に訴えました。彼自身は「個人的に何とも思っていない」とコメントを返します。そして、「非人道的な兵器ではありません。使用したことに対し、謝罪するつもりはありません」と続けています。
そうしてジョン・ハーシーとウィリアム・ショーンは、「舞台裏をもっともっと探るべきだ」と感じました。政府の記者会見や演説、報道の制限は、望み通りの効果をもたらしていました。全米の抗議や警戒の声は、制御できるざわめき程度に収まっていたのです。「原爆はアメリカが抱える兵器の中では妥当な主力兵器であり、核の未来である」という考えが、関心を失いつつある国民に受け入れられていきました。ほとんどのアメリカ人が、何が起きたのかが完全に明らかになる前に、広島や長崎への関心を失ってしまっていたのです。
しかし『ニューヨーカー』のチームは、広島で起きたことの本当の意味や、原爆投下が人類に何をもたらしたのかという点について、釈然としない思いを強く抱き続けていたのです…。
「この兵器の、信じられないほどの破壊力を理解している人はほとんどいません。核兵器の使用がもたらす恐ろしい意味を考えるとくが来たのです」と、彼らは『ヒロシマ』の本を締めくくっています。
ハーシーとショーンは、ハーシーが日本で取材を行って、「建物ではなく人にどのような影響があったのか」について書くことを決断します。彼らはどのような切り口になるかはまだわかりませんでしたが、「やらなければならないことだ」ということは確信していたのです。もし東京にいる記者たちが書かない、もしくは書けないのであれば、それを『ニューヨーカー』が引き受けようと立ち上がったのです。
ショーンと上司のハロルド・ロスは、その年の初めにも記者のジョエル・セイヤーが連合軍とともにドイツにわたり、コロンの大空襲の惨状を民間人の視点から記事にしようと準備していました。この記事は実現しませんでしたが、同じアプローチを広島の調査に使うことができると考えていました。
国家や民主主義や良識の名のもとに、投下された原爆の実態を理解し、世界に知らせるとともに広島と長崎の犠牲者の顔と運命を明らかにするときが来たのです。不十分な統計やありきたりな瓦礫(がれき)の写真は、このような真実を語る妨げとなっていました。また、日本の被害者を非人間化することによって、アメリカ国民は兵器について自己満足していたとも言えます…。
第二次世界大戦を通してハーシーは、非人間化がいかに戦争の卑劣な行為を可能にするかを目の当たりにしてきました。ローマでの民間人に対する空襲やナチス強制収容所における残虐行為の「無慈悲な野蛮さ」を、彼自身の目で見ていたからです。
戦争中は多くのアメリカ国民同様に彼自身、「日本人を野蛮な敵だ」と見なしていたのは事実です。それでもガダルカナル島の戦いを取材中、自分に銃を向ける日本人が人間であることを、そして誰かの息子であり、夫であり、父であることを忘れないようにしていたのです。
「長い間、日本人のことを憎んでいました」と、彼は直後に書いています。そして「敵というイメージのもと、どこまでも憎むことができた」とも話しています。「ですが、兵士個人を憎むことはしませんでした。彼は箱根出身かもしれないし、もしかしたら北海道かもしれない。リュックサックにはどんな食べ物が入っているのだろう? 徴兵されたとき、どんな希望を奪われたのだろう? などといったことを考えました…」と語っていました。
広島と長崎への原爆投下に至った戦争によってハーシーは、「人間の悪」を目の当たりにし、さらに自分も同じ人間を完全に見下せる人間であることに気づいてしまったと語っています。そして、「もし文明に意味があるのなら、私たちは惑わされて殺意を持った敵にさえ、人間性があることを認めなければならない」と改心したことを告げています。
そんな想いとともに彼は、広島へ向かったそうです…。
Source / TOWN & COUNTRY
Translation / Yuka Ogasawara
※この翻訳は抄訳です。