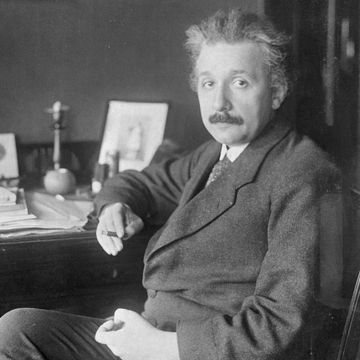北川景子の演じる茶々のあざといまでのすごみがNHK大河ドラマ『どうする家康』で好評だ。母であるお市の方と二役だが、お市の方としては、本当は家康と結婚したかったという無理な設定もあり、戦国きっての美女として適役というだけで終わっていた。
だが、秀吉の側室・茶々として再登場するや、北ノ庄での母との別れのときに「私が天下を取る」と約束した怖い戦国の女性を見事に演じている。
松本潤が演じる家康もたじたじなのだが、結局、茶々は家康に負けて豊臣家は大坂夏の陣で滅びてしまう。今回は、茶々のどこが間違っていたのかという観点から歴史を振り返る。
ドラマでは、関ヶ原の戦いにおいて、茶々が石田三成の黒幕で、寧々は家康に好意的に動いたということになっていた。しかし、それは間違いで、寧々は西軍寄りで、茶々は妹の江が秀忠夫人なので煮え切らず、三成に軍資金も出さず、毛利輝元の出陣も邪魔したのである(ダイヤモンド・オンラインで掲載の、『【どうする家康】関ヶ原の戦い「寧々は家康側」は本当?江戸時代からの“都市伝説”の真偽』参照)。
茶々にとって、東軍の大勝利は計算外だっただろうが、家康もとりあえずは、豊臣政権の大老としての立場で天下を差配する建前は維持したし、大坂城へも伺候していた。
1603年に伏見城で征夷大将軍となるが、これを「幕府を開いて天下を差配することになった」というのは言い過ぎだ。幕府という言葉も当時はなかった。
そもそも家康が将軍になったことは、意外なことではなかった。足利義昭が秀吉より1年前に亡くなり、足利宗家は跡取りがいなかった。
源氏長者も、元は村上源氏の久我家だったが、義満の時に足利家に移り、空席になっていた。
となると、源氏で官位が最高位は家康だから、氏長者となるのは自然だし、東日本を治めてもいる。また、坂上田村麻呂が征夷大将軍となった前例もある。
このとき、秀頼が同時に関白となるといううわさもあり、公家の山科言継も日記に書いている。徳川家が将軍で、豊臣家が関白というのは、公家衆の感覚としておかしいことではなかった。秀頼関白は実現しなかったが、内大臣に昇任したので、「いずれは」と言われて茶々も納得した。
かねて話があった千姫の輿入れも実現した。秀頼が11歳、千姫が7歳だから夫婦としての実態があろうはずもなく、婚約に近いが、将来の縁組みを前提として婚家に移るのはよくあることだ。
江は従兄弟の佐治一成の元に幼少時に輿入れしているし、秀忠の次女・珠姫は3歳で前田利常と結婚し、金沢に事実上の人質として送られている。
ドラマでは、茶々が家康に強引に迫って輿入れを実現したとしていたが、現実は逆だろう。ただ、母親の江が身重の体で江戸から千姫に付き添って上洛したのに、家康に大坂まで行くことは止められ、伏見で留め置かれたのは、姉妹で話をすることを家康が嫌ったからだろう。天下の仕切りを姉妹で談合されてはたまらない。
この年は、出雲阿国が、六条河原での念仏踊りで評判を取ったが、女性が大活躍する時代だった。
江と前夫の小吉秀勝(関白秀次の弟)との娘である完子は、茶々の養女になっていたが、1604年に、九条幸家に豊臣家の姫として輿入れさせ、茶々は豪華な御殿まで建てて、京の人々を驚かせた。
このころ江戸では、江が家光を生んだ。これで、豊臣家にも徳川家にも、浅井や織田の血が流れることになり、大坂城で茶々の側近だった織田信包、長益、信雄らにとっても大きな喜びだった。織田・浅井・豊臣・徳川連合王朝の趣だった。
8月に、京で秀吉の七回忌に豊国神社の臨時祭が開催されたが、都が始まって以来といわれるにぎわいとなり、京の民衆に秀吉がいまだ慕われていることを家康に見せつけることになった。
大河ドラマでは、秀吉が「秀次切腹事件」などの晩年の「暴虐」や朝鮮の役などで嫌われていたと描かれているが、これは真っ赤なうそである。応仁の乱で荒れた京を復興し、朝廷の威信を回復し、平安建都以来の大改造を施して近世都市としてよみがえらせてくれた恩人に対する当然の評価だった。それに対して、徳川政権の政治の嫌われぶりは明らかだった。
1605年には、第2代将軍に秀忠がなった。これについて大河ドラマでは、豊臣に天下を返すつもりがない意思表示だったと描かれていた。だが、徳川家が将軍であっても、豊臣の臣下であるとか、対等の立場だというのは可能なので、論理的ではない。
茶々が怒ったのは、秀頼に対し、秀忠の将軍宣下を祝いに上洛しないかと打診があったからだ。「無理にと言うなら秀頼と心中する」といった物騒なことを口走ったとされる。茶々は思い詰めると極端な言葉を吐くことがあった。
ただし、茶々が上洛に反対した理由は、秀頼が将軍秀忠に臣従することになるからではない。のちに二条城で家康と秀頼が会見したときも、家康のほうが官位が高いことに応じた儀礼上の配慮はあったが、臣従とはいえない。
仮に秀忠が将軍になったときに秀頼が上洛しても、公家衆と将軍が会うときと同じで、官位が高い秀頼が秀忠の下になることはあり得ない。千姫の父なのだから、せいぜい対等の立場で接することになっただけだろう。
茶々が心配したのは、秀頼の身に何か起きるとか、そのまま京都とか伏見に留め置かれることだった。その後の茶々の行動を見てもわかることだが、茶々は秀頼の身に何か起こるとか、自分と引き離されるというのを極端に恐れた。
前田利長の母であるまつが江戸で人質にされ、のちに利長が越中高岡で重病になっても見舞いの帰国を許されなかったという無念を思えば、仕方ないことだろう。
いずれにせよ、家康も刺激が強すぎたと思ったのか、秀頼を右大臣に昇任させ、六男の松平忠輝を大坂に派遣して、秀頼に拝謁させるなど、慰撫に努めた。翌年、江戸では江が次男の国松(のちの駿河大納言忠長)を出産した。
1607年に、家康は伏見城から駿府城に引っ越した。今川家の人質として長く駿府にいたので、故郷そのものだ。富士山が見えることも気に入った理由である。幕府の実務を江戸の秀忠に部分的にせよ譲ったので、連絡を取りやすくする必要が出たこともあろう。
茶々は、秀頼に「教育ママ」ぶりを発揮した。清少納言を生んだ清原家の流れをくみ、後陽成・後水尾天皇の侍読(家庭教師)で最高のインテリでもあった舟橋秀賢に、政治・法律・軍学・漢籍・和歌などを教授させた。
また武芸では、最後の近江守護だった六角義治に弓矢を教授させるなど、当時としては最高の教育レベルで、家康の子どもなどとは比べものにならないものだった。
1608年には、秀頼と侍女との間に国松が生まれた。秀頼は16歳となった一方で、千姫はまだ幼かったので、ごく普通のことなのだが、子どもが男子だけに扱いが難しく、叔母である初が若狭で、身元を明かさずに里子に出した。
2月には、痘瘡に秀頼がかかり、危ないとのうわさも流れ、福島正則らが見舞いに訪れたが、なんとか無事に回復した。京では、前の年に北野天満宮の新社殿を造営した功徳で助かったといわれた。この頃、秀頼は出雲大社など全国で多くの社寺を造営したが、桃山風の華麗なものだった。
1609年には、木下家定が亡くなり、寧々は政治的な動きをやりにくくなった。しかも、寧々が嫡男の勝俊にすべて継がせるように命じたことに対し、家康は「自分に相談なくそんなことを命じた」として、寧々を「もうろくしている」と罵倒し、いったんは取りつぶしになった(大坂夏の陣の後に再興)。家康が寧々を大事にしていたことなど一度もない。また、この年、秀頼に天秀尼が生まれた。
このころ、若くして死んだ家康の四男忠吉の後、九男の義直が尾張に入り、名古屋城を築き始めた。豊臣恩顧の大名たちが天下普請として手伝わされ、福島正則などは大反発した。
1611年には秀頼が、秀吉が亡くなってから初めて上洛し、二条城で徳川家康と会談した。後陽成天皇から後水尾天皇への譲位の機会に5年ぶりに家康が上洛してきたので、一度会いたいということだった。茶々は、このときも、秀頼の身の安全を心配して嫌がったが、加藤清正らが勧め、占いでも「吉」と出たので、しぶしぶ承諾した。
清正と浅野幸長が同行し、福島正則は腹痛を口実に、万一の時に大坂城を守る体制を取った。船で伏見に着いたのを迎えに来た家康の子の義直や頼宣に、清正は秀頼に対して臣下の礼を取らせた。
二条城では対面して座ったものの、杯は家康が先に空けた。秀頼は、卑屈にはならずに年長の家康を無理なく立て、称賛された。会談は、清正が頃合いを見計らって「茶々が大坂で待っているから」と秀頼に退席を促して終わった。
清正らは無事に会談が終わって大満足だったようだが、この会談は失敗だった。家康は秀頼について「女に囲まれて育ち、嬰児のごときと聞いていたが立派に育っている」「賢き人だ。人の下知など受けまい」といったという。
どこから見ても優れた人物というのではなく、カリスマ性があって、へつらいながら立ち回るタイプではない、いかにも扱いにくい若者だとみたのである。
もし、秀頼がバカ殿のように振る舞ったり、へつらって家康を持ち上げたりすれば良かったのだが、そうではなかったため、家康は不安になった。
秀頼が普通の一大名のように振る舞うことまでは期待しなかったが、「徳川の客分」のような立場で満足してくれれば良い、ということだった。ちょうど、古河公方と北条家とか、京極家と浅井家などの関係のようなものだ。
しかし、諸大名が秀頼に会ったら、「さすがは天下人だ」と思うだろうと恐怖が増した。
しかも、このとき京の民衆は、秀頼の行列を一目見ようと都大路に出て歓迎し、清正は御簾を上げて立派に育った秀頼の姿を見せた。家康が「豊臣滅亡すべし」と決意したのは、このときだったのではないだろうか。
*本記事は寧々の視点から描いた『令和太閤記 寧々の戦国日記』(ワニブックス)を再構成した。