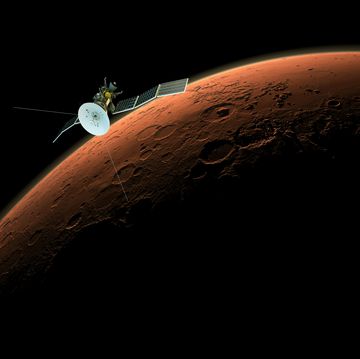- スイス連邦工科大学チューリッヒ校の研究チームが、宇宙探査における歩行ロボットの有用性についてまとめた論文を発表しました。
- 探査車は1台で探査を行っていたのに対し、歩行ロボットはチームで動きます。
- 歩行ロボットが抱えていた「凸凹のある地面で転倒しやすい」という弱点はほぼ克服されており、今まで困難だとされていた場所の探査もできるようになることが期待されています。
歩行ロボットが
月面探査をする日も近い
漆黒の闇のような空へと一直線に伸びるヘッドランプの光。未知の星に広がる岩だらけの地面を進む3人の探検家チームは、まるで動物が本能的に危険を察知するように危険な岩場や災難を予測し、計算どおりに歩みを進めます。そして調査対象となる環境を慎重に探し出した後、このチーム唯一の科学者メンバーが顕微鏡と分光計を使って物質を分類し、その結果を地球のサポートチームへとその情報を伝えます…。
まるでSFの世界のようなこの探検の様子は、現実の世界で2022年8月に行われたものです。ただし実際は、「知の星に広がる岩だらけの地面」とは“スイスの採石場”で、「3人の探検家チーム」とは宇宙飛行士ではなく“歩行ロボット”による演習になります。
歩行ロボットは最近、米ボストン・ダイナミクスの犬型ロボット「スポット(Spot)」が音楽に合わせて踊るムービーが話題になるなど、ネット上でよく見かけるようになっています。しかし、これらのロボットはまだ最終的な特定の用途が決まっているわけではなく、可能性は流動的です。
スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH)ロボティクスシステム研究所の博士課程に在籍するフィリップ・アーム氏はこうした歩行ロボットに、警察や軍隊の防衛用といった地上でのニーズ以外に利用できる可能性を見込んでいます。
「スポット」によるキレキレのダンスをぜひご覧ください。
アーム氏は、『ポピュラー・メカニクス』誌に次のように語っています。
「ここ数年で、(歩行ロボット工学は)非常に成熟し、実際にさまざまなシーンで使用できるようになりました。私たちは、『歩行ロボットは地球上の実に困難な環境で機能している。だったら宇宙でも試してみるべきではないか?』と考えたのです」
アーム氏が筆頭著者としてまとめた論文がこの夏、ロボット工学やそれに関する最新技術にフォーカスした科学雑誌『サイエンスロボティクス』誌に掲載されました。この論文では、「月や火星などの地球外探査において、四足歩行ロボットのチームがいかに従来型の惑星探査機よりも優れた性能を発揮できるか」という点について考察されています。
歩行ロボットが
もたらす可能性
1990年代半ばに登場した火星探査車はこれまで、火星表面上をゆっくりと移動して新たなデータや画像を収集し、科学者の研究に寄与してきました。ですが、こうしたタイプの探査機の主な移動方法となっている車輪走行には問題があることもわかっています。例えば火星探査車「スピリット」は、2010年に柔らかい砂地に車輪がはまって 「運用終了」となってしまいました。その姉妹機「オポチュニティ」も、同じミッション中に一時砂地で動けなくなる事態に陥っています。
ウェストバージニア大学のユー・グー(Yu Gu)准教授(機械・航空宇宙工学)は、自身の研究室でロボット探査の研究を行っています。グー氏は 『ポピュラー・メカニクス』誌の取材(メールでの回答)で、「車輪走行は惑星探査の初期の段階ではうまくいくものの、その有用性は限定的だ」と指摘しています。グー氏の見方は次のとおりです。
「月や火星のような比較的簡単な場所であれば、車輪走行は十分に可能です。米航空宇宙局(NASA)の火星探査ヘリ『インジェニュイティ(Ingenuity)』のような飛行手段は便利だと思われますが、複雑な地形や地下洞窟に入っての探査ということになれば、新たな移動手段を導入することで多くの可能性が現実化できるでしょう」
アーム氏らの研究チーム以外にも、次世代ロボット探査の開発に関心を持つ研究者は増えています。その一つがジェット推進研究所(JPL)のNeBula(Networked Belief-aware Perceptual Autonomy)プロジェクトチームです。このプロジェクトチームは最近、洞窟内での歩行ロボット模擬探検を行っており、ボストン・ダイナミクスと共同で犬型火星探査ロボットのプロトタイプ開発に取り組んでいます。
以前は2本、4本、あるいはそれ以上の脚を持つロボットは、凸凹のある地面で転倒しやすいのが弱点でした。ですが、グーとアーム両氏によれば、この問題はほぼ克服されているそうです。「仮に歩行ロボットが転倒したとしても、ミッションが未完のまま終了してしまうような事態にはならない」と見ています。
そしてグー氏によれば、「転倒は探査車にも起こり得ること」と前置きをしたうえで、「元の状態に戻れる方法がある限り、転倒は歩行ロボットの致命的問題にはならないはずです」という見方を示しています。
両氏は、「むしろ歩行ロボットに関して本当に懸念すべきところは、その複雑さです」と指摘します。歩行ロボットは探査車よりも機械的に複雑なため、「エネルギー効率が悪く、新たな種類の機械的故障に弱い」という問題が、可能性として考えられるということ…ですが、こうした懸念も、「このロボットがもたらすと思われる利点を上回るものではない」と見込んでいます。
歩行ロボットの
知能が上がっても
人間の存在は不可欠
アーム氏のチームは、月面の岩だらけの地形だけでなく、ロボットと地球の管制官との間の通信の遅れも模擬想定したシナリオで研究を行いました。
SFドラマシリーズ「スタートレック」では、物質を分解して転送ビームに乗せて運んで目的地で再構築するビーム方式の転送装置を使用しています。映画『スタートレック ジェネレーションズ』(1994年)であれば 、“Beam them out of there, Scotty(転送を頼む、スコッティ)”の合図で機関主任モンゴメリー・スコット(愛称:スコッティ)が送り出した探査チームのように、アーム氏の実験で用いられたロボットは「スカウト」「サイエンティスト」「ハイブリッド」の3体1組で探査をするというわけです(さすがに、転送装置の開発までには至っていません)。
「スカウト」がまずはそこの環境を評価し、調査対象のターゲットを特定します。すると、続いて「サイエンティスト」がアームに内蔵された2つの機器(ターゲットの化学的組成を特定するラマン分光分析装置とマイクロスコピックイメージャー)を使って分析を開始します。そして3体目の「ハイブリッド」が一定の科学分析を行いながら、必要に応じて他のロボットの支援もするように設計されているとのこと。
アーム氏は次のように説明しています。
「この実験で1体のロボット単独、もしくは同一構造のロボットを複数使うよりも、今回のアプローチのように異なる役割を果たす機能を擁するロボットを数体用意し、チームを組ませて分担で役割を分けて探査を行ったほうが、はるかに迅速かつ効果的であるということがすぐにわかりました。
そこで私たちは、ロボットが忠実に自分の役割を繰り返すこともわかりました。ロボットがいくつかのタスクに対して、ある程度の専門性を持っていればいいのです。そうすれば、より効果的かつ効率的にロボットを使用することができます。つまりロボットは、1台で全てができるようにする必要はないことがわかりました」
✅ 「VIPER」とは何か?
歩行ロボットは今後の地球外探査でより多くの役割を果たすことが見込まれ、その準備が進められていますが、だからといって探査車がすぐにお役御免になるというわけではないでしょう。再び宇宙飛行士を月に送ることを目指すNASAのアルテミス計画の一環として、新たな月面探査車VIPER(Volatiles Investigating Polar Exploration Rover)のデビューが予定されています。火星探査車同様にVIPERには、凸凹のある月の表面専用に設計された4つの車輪が付いています。
VIPERは現在、2024年末までに打ち上げられる予定であり、100日間のミッション期間中に、月面に氷などの資源が存在する可能性を探査することが任務です。VIPERが行うのはNASA初の資源マッピングミッションであり、将来の有人探査ミッションにおいて安全に居住できる場所を特定するうえで、重要な役割を果たします。
将来的に月へ行く宇宙飛行士が、これらの資源を収集する際には歩行ロボットが活躍するかもしれません。ですが、やはりVIPERのような探査車には、1台で探査をこなしてきたという実績は無視できません。
この演習で歩行ロボットチームは、68分かけて採石場の1375平方メートルを進み、12個の調査ターゲットを特定しました(ちなみに火星探査車は、火星日1日<約24時間と40分>あたり約100メートルしか進めないように設計されています)。
ただ、この実験では1つの課題に直面しました。その問題とは、「想定される5秒間の通信遅延を踏まえて、データをいかに効率的に地球に送信するか?」という点においてです。アーム氏は次のように述べています。
「かなり早い時点で、これは当初の想定よりもずっと難しいことだとわかりました。全てが遅延するという事実だけで、標準的な遠隔操作手順は基本的に実行不可能になるからです。実際に直接制御するのは非常に困難なので、実に高度な自律性が必要になります」
ロボットがより高いレベルの自律性を獲得すれば、氷で覆われた土星の衛星「エンケラドス」の内部のような、地球からもっと遠い惑星のさらに困難な場所の探査に役立つという点に、グー氏も同意しています。しかし、たとえロボットチームの知能がもっと高くなり、単独で宇宙を探査できるようになったとしても、人間は常にこの問題には不可欠な存在だとアーム氏は考えます。
「宇宙探査の将来の姿はきっと、人間とロボットの共同作業になると考えています。人間は指示監督役を担うことになるでしょう。(中略)人間の創造性と知性は、やはり比類なきものですから」
例えば、将来の宇宙飛行士は安全な居住空間から土壌サンプルの分析に専念し、ロボットはクレーターを測定し、サンプルを採取するという具合です。グー氏も、「人間の宇宙飛行士が到着する前に、着陸地点の居住環境を準備することもロボットの重要な役割になるのではないか」と指摘しています。
現在、NASAの有人宇宙飛行ミッション「アルテミス」の打ち上げ予定は約2年後に迫っており、アーム氏によれば「こうした歩行ロボットのデビューがそれに間に合うかどうか? は状況次第、不透明です」ということです。
「本当に興味深いのは、アルテミス計画による後押しだけでなく、多くの民間企業が宇宙や宇宙開発分野に参入し、実際に一定の競争状態をもたらしているということです。実現にはまだ少し遠いというのが実状ですが、ニーズが十分に明確であれば、数年以内に何らかのテクノロジーを送り出せるようになるような推進力が生まれる可能性は確実にある、と思っています」
Translation / Keiko Tanaka
Edit / Satomi Tanioka
※この翻訳は抄訳です